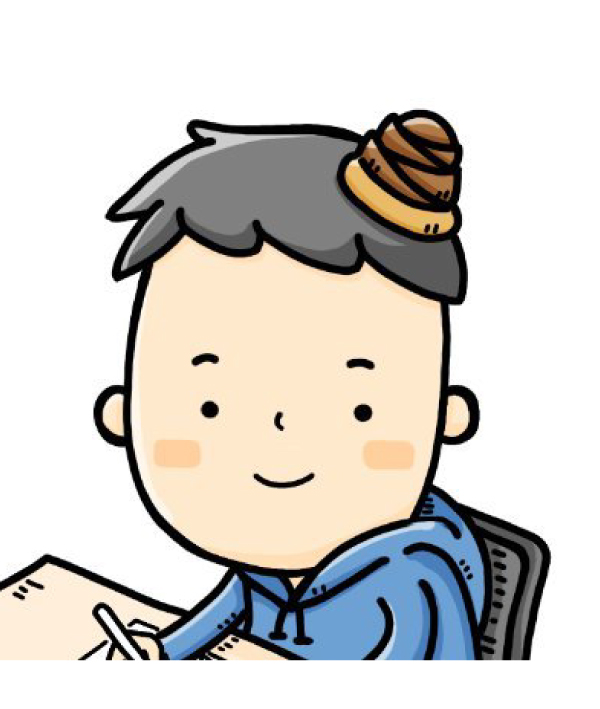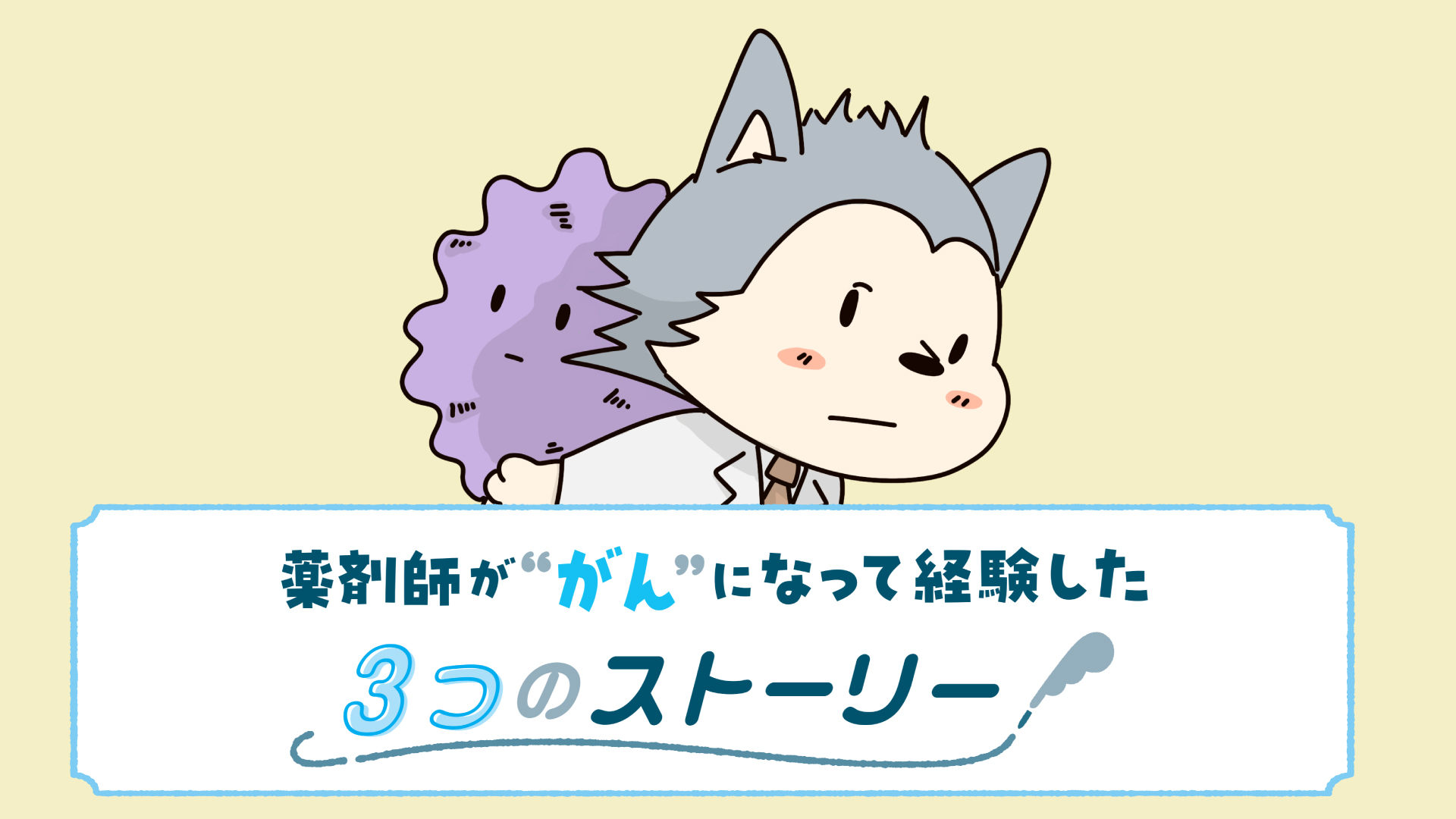人と人とのつながりが人を健康にする

私は,2023年8月28日に手術で小腸の腫瘍を切除しました。しかしながら大腸にも腫瘍があり,術後の診断では「大腸にある腫瘍はおそらく転移したがん」であるというものでした。また,手術で切除した小腸のがん周囲のリンパ節への転移は,生検に出してみないとわからないと説明を受けました。この先の不安と手術による痛みが入り混じるなか手術を終え,ようやく「ファーストステップを乗り越えた」という達成感みたいなものを感じました。
手術後,3~4日程度経過すると食事が摂れるようになってきます。最初はジュースからはじまり,ごはんは五分粥,七分粥と少しずつ,1週間程度かけて固形食に戻していきます。9月4日の夜,看護師さんから「明後日退院してよい」と伝えられ,ようやく病院の外に出られるという嬉しさがこみあげてきました。
しかし,夕飯を終えたころから寒気を感じるようになり,体温を測ってみると39℃の高熱で,翌日の退院は延期となってしまいました。新型コロナウイルス感染症の疑いもあるとのことから,翌日にコロナ検査および細菌感染検査が実施されました。幸いにも新型コロナウイルス感染,細菌感染ともに陰性でしたが,手術により縫合した箇所に小さな穴があいてしまい,そこから腸液が漏出してしまっていることが発熱の原因であることが判明しました。当時の私が記載した日記が,何ともいえない感情を物語っています。
9月9日の日記
色々と限界に感じる今日この頃です。なんの前触れもなく急に入院し約1か月怒涛の如く何とか苦難を乗り越え,あと少しで第一関門突破という場面でハシゴをはずされた感覚です。栄養も充分ではないことや睡眠不足,痛み,不安ありますが,些細な事に本当にイライラします。点滴を3種類しているために,かなりの頻度で看護師さんが入り,その都度起きてはマスクを着用し,バーコードを見せて,名前を伝えます。そんな,なんということはない,一つ一つが物凄く負担に感じるものです。重病を乗り越えた人の本を読んで,その著者のような受け入れをしたいと思っても,まったくそうは考えられないのも皮肉なものです。未熟さゆえ,知識と実践はそう簡単には結びつかないのでしょう。
〔Facebookへの投稿より抜粋(原文ママ)〕
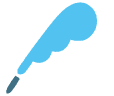 科学的根拠がない言葉の大切さ
科学的根拠がない言葉の大切さ
2日に1回,土曜日,日曜日も関係なくレントゲン室に行き,検査を受ける日々でした。がらんと静まり返ったレントゲン室の前の椅子に座り,検査のために名前が呼ばれるのを待っていると,レントゲン室で同じく検査の順番を待っていた80代くらいの男性が私に声をかけてくれました。
「おたくは何のがんなんですか?」
その一言から会話が始まり,レントゲン検査が終了した後も,さまざまなお話をしました。その方は,82歳の胃がんを患った男性で,手術で胃を半分くらい切除したとのことでした。また,お互いの病気のことだけでなく,仕事のこと,家族構成などいろいろな話をしました。「がん患者」であるという共通点をきっかけに,こんなにも距離が近づくのだと驚きを感じました。
この男性の言葉のなかに心を打たれたフレーズがあります。
「がんを治すのは治療でも薬でもなく,自分自身なんですよ……」
私自身,薬剤師であり科学的根拠のない言葉に,どこまで説得力があるのか疑心暗鬼に思っているところがあります。しかし,この科学的根拠のない短いフレーズに「この苦しい状況が自分以外の何かのせいだ……」と心のどこかで思いながら生きていたことに,はたと気づかされました。
その男性とともに病棟の7階までエレベーターで上り,握手を交わしながらお別れをしました。その際「あなたは良い面構えをしている。だからきっとうまくいきますよ!」と声をかけてくれました。勇気づけてくれるその言葉は「ああ,この先どんな厳しい化学療法が待ち受けていようとも,厳しい道のりになろうとも,頑張ろう!」と,そんな気を起こさせてくれました。同じ境遇にある人の言葉が,こんなにも身体に染み渡るとは,がん患者になるまで想像もしていませんでした。
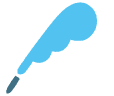 薬局に活かせる視点(マギーズ東京から学ぶ)
薬局に活かせる視点(マギーズ東京から学ぶ)
私と同じように,がん経験者同士が話し合うことで前向きに,そして勇気づけられるような場所はないだろうかと探していたところ,がんの経験者でありながら薬局という資源を活かして医療をより良くしていこうと働きがけている鈴木信行さんから「マギーズ東京」という場所を紹介してもらいました(写真)。

(後列左:鈴木信行さん,前列左:筆者,前列右:筆者の妻)
〔手術を終え,化学療法4クール目の体調が良いときを見計らって見学に行った際に撮影〕
マギーズセンターは,マギー・ジェンクスさんが乳がんを患った経験から1995年に創設した施設で,現在では世界各地にあります。また「部屋に自然光が入って明るいこと」「水面が見える,もしくは暖炉や水槽があること」「安全な中庭があること」など,マギーズセンターの国際建築要件を満たす必要があります。わが国では「マギーズ東京」が国内唯一のマギーズセンターであり,見学させていただきましたが居心地のよい素敵なところでした。なかで働く方々は看護師や心理士を中心に構成されており,気兼ねなく相談や話ができるというのは,毎日死を意識せざるを得ない当事者にとって安らぎを与えてくれる空間です。
ちなみに最も感銘を受けたのはトイレのスペースでした。トイレはやや広めに設計されており,その理由を聞いたところ「1人で泣けるように……」との配慮からきているとのことでした。この他にも,初めての訪問であっても気がつくほど,どこまでも利用者目線で作られた施設に私は感謝しかありませんでした。
マギーズセンターのような,時には当事者同士が集まり話し合い,時に主治医とは異なる専門家へ相談ができる場,そんな役割を全国各地に多数存在する薬局が担えたら,よりいっそう,患者にとって求められる優しい社会になるのではないだろうか……と考えます。
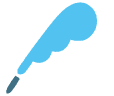 まとめ
まとめ
米国の政治学者であるロバート・パットナムは『ソーシャルキャピタルとは,人々の協調行動を活発にすることによって,社会の効率性を高めることのできる「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴である』と定義しています。
社会や地域コミュニティにおける人々の相互関係や結びつきを支える仕組みの重要性を説く考え方のことですが,健康との関連性が強いことが数々の研究で報告されており,医療業界でも大変重要視されてきました。適切な医薬品や治療が存在することががんという疾患を乗り越えるうえで,必要不可欠であることは間違いありません。しかし,それだけでは患者の「気持ち」は救われないのかもしれません。なぜなら「心強い妻がいる」「毎日のように気にかけてくれる家族がいる」「病状を気遣ってくれる職場の仲間や友人がいる」など多くの人々のつながりや何気ない会話や関わりが,私の治療を手助けしてくれていることを,この半年間を通じて大きく実感したからです。
幸運にも私は周りの人々や医療に恵まれましたが,そうではないがん患者も大勢いるはずです。高齢多死の時代を迎えるわが国では,今後もがんとともに生きる人々は増えていくことが予想されます。そのなかで患者との距離が近く,アクセスしやすい,薬剤師や薬局がソーシャルキャピタルの一つのリソースになっていくことを1人の患者として期待しております。