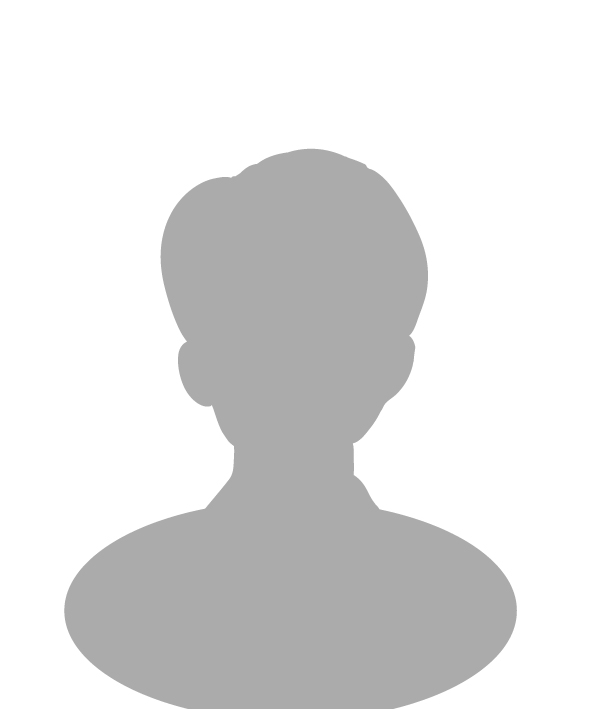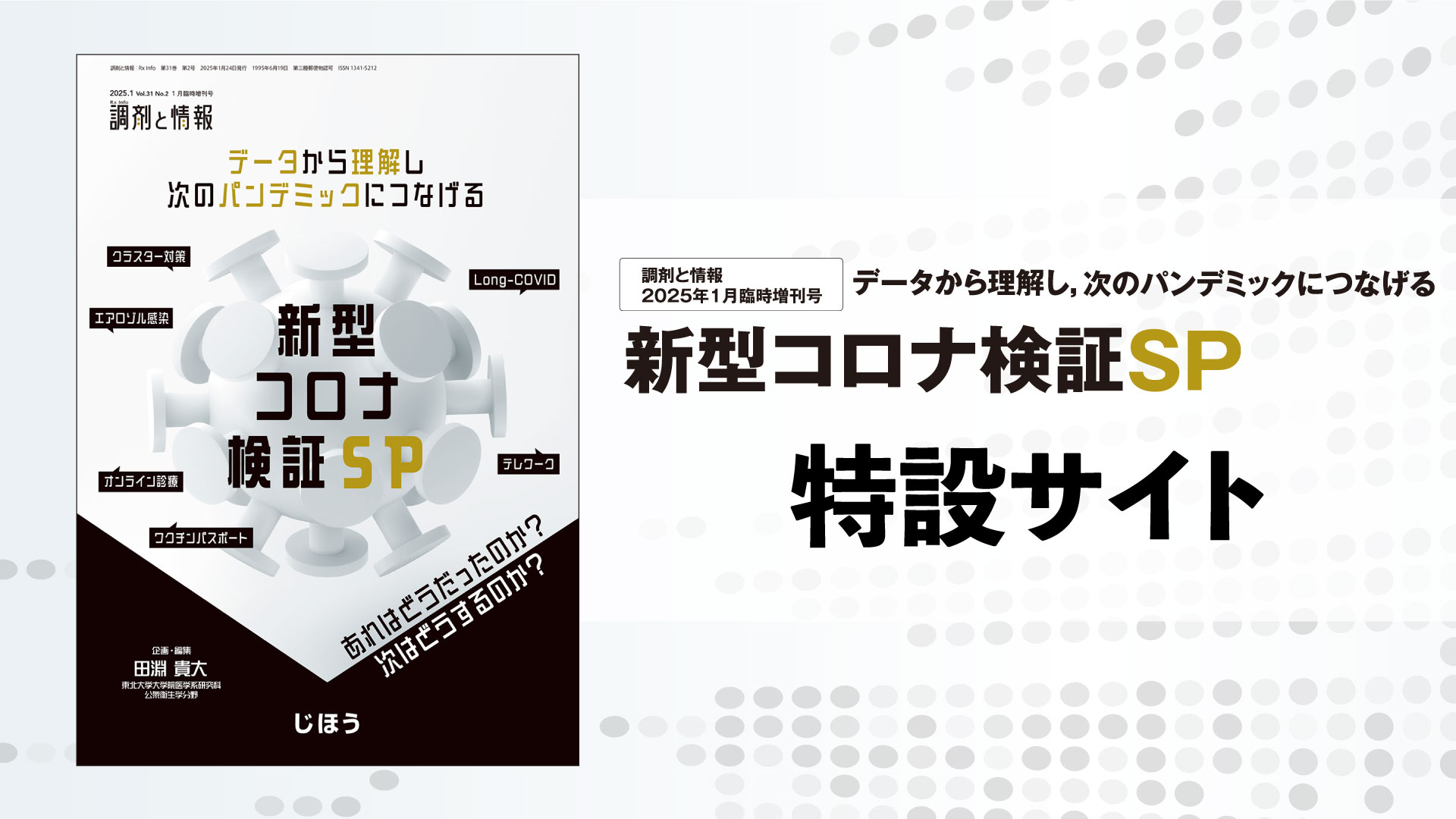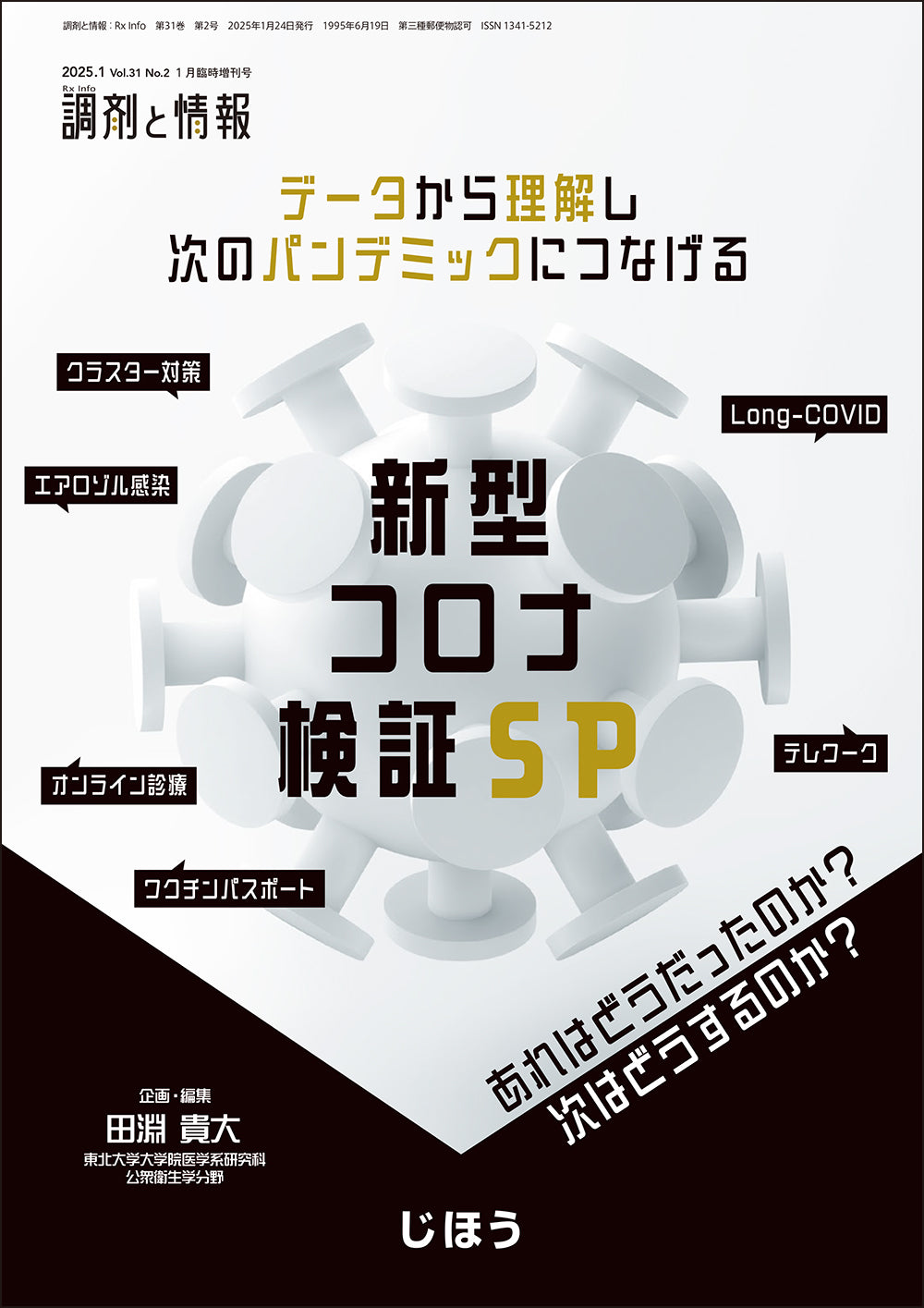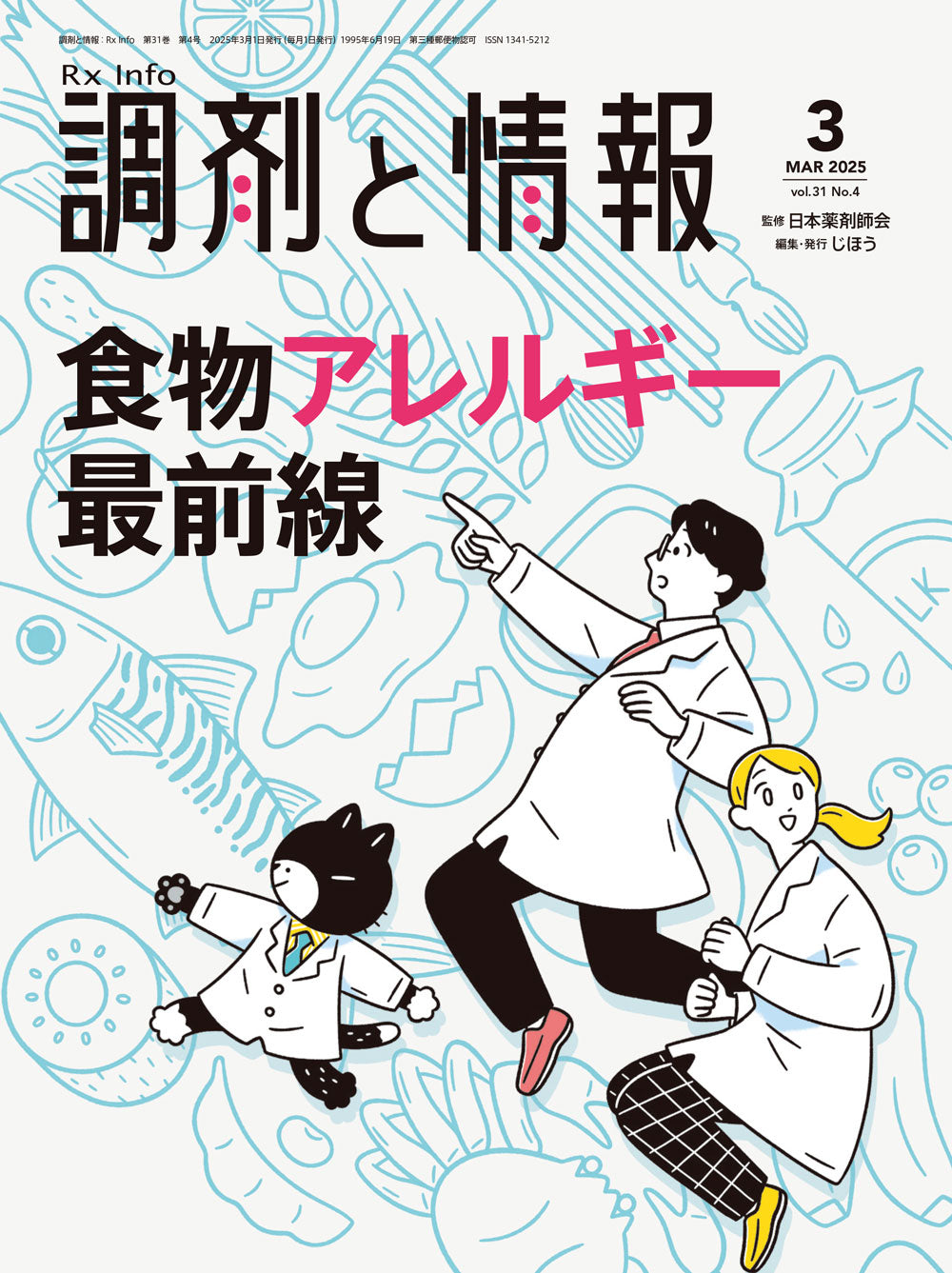【Interview】『調剤と情報』2025年1月臨時増刊号 企画・編集者に聞く
【Interview】『調剤と情報』2025年1月臨時増刊号 企画・編集者に聞く
データから理解する 新型コロナ検証SP

—— 「新型コロナ検証SP」について教えてください。
(田淵)本臨時増刊号の目的は,新型コロナウイルス感染症が社会に与えた影響をデータとともに検証し,次のパンデミックにどう備えるかを考えることです。新型コロナウイルス感染症は,感染症対策だけでなく,政治,経済,社会のあらゆる側面に影響を与えました。そこで本臨時増刊号では,さまざまな専門家に寄稿いただき,科学的根拠に基づく検証を1冊にまとめ,議論や検討をはじめるための「第一歩」という位置づけで企画しました。
—— なぜ “今 ”,新型コロナウイルス感染症をテーマにしようと考えたのでしょうか。
(田淵)新型コロナウイルスによるパンデミックが発生した当初,われわれはさまざまな情報に右往左往させられました。本来であれば,そのようなタイミングで,社会に必要な情報を提供していくことが重要ですが,実際にはそれが非常に難しいということを,コロナ禍を通じて経験しました。
今回,本臨時増刊号の企画・編集を務めさせていただく背景として,JACSIS/JASTIS研究というものがあります。JACSIS研究の目的は,新型コロナウイルス感染症問題を含めた住民の生活・健康・社会・経済活動の実態に関する調査,データ分析を行い,科学的根拠に基づいた「住民の健康と社会活動を守る」ための現実的な社会経済的救済策や健康増進策の立案につながる情報提供を行うというものです。本プロジェクトを2020年3月に立ち上げて以降,非常に多くの論文がさまざまな研究者から発表されています。
次のパンデミックは必ずやってきます。いま出揃いはじめている研究成果を吟味し,検討するのに良いタイミングだと思いました。本臨時増刊号の「はじめに」のところで,執筆いただいている古瀬祐気先生(東京大学 新世代感染症センター 感染系微生物学分野)の「エビデンスは更新され続けるものであり,データに基づくエビデンスであっても一つの真実を示すとは限らない。そして,公衆衛生対策など社会的決断が必ずしもエビデンスに基づいてなされるわけではないことを,このパンデミックを通じて私たちは学んでいった」1)という言葉を紹介しました。この言葉にもあるように,エビデンスは常に更新され続けるものであり,一つのデータで「真実」が決まるわけではなく,どんどん検証をし続ける必要があります。本臨時増刊号が,そのきっかけになればと考えています。
—— コロナ禍のとき,「新型コロナウイルス」「ワクチン」などを対象に陰謀論や誤った情報が氾濫したことも,記憶に新しいところですが,公衆衛生の専門家として「インフォデミック(情報の氾濫)」についてどう考えていますか。
(田淵)新型コロナウイルス感染症の話に限定すると,陰謀論や科学的根拠のない情報がSNSなどを中心に氾濫しました。また,それは情報の出所が不明なものだけでなく,トランプ大統領などの政治家からも発信されています。
社会が不確かな状況のなかにあるときに,政治家からの不確かな情報の発信は,社会に大きな影響を与える可能性があり,インフォデミックに対する対策を考えるために検証される必要があると思います。また,パンデミックのような緊急事態下においては避けられない側面もありますが,専門家の意見と政治的判断が交錯し,必ずしも明確な根拠に基づかない決定が下される場合もあります。例えば,オリンピックの開催やワクチンパスポートなどが例として挙げられますが,しっかりと検証していくことが大切なのではないかと思います。
一方で,インフォデミックには情報を紛れさせるという特徴もあります。この特徴を使っている例がタバコ企業です。さまざまな情報が溢れているなかで,実はタバコに関するニュースは極端に少ないのですが,インフォデミックでさまざまな情報が多いので,タバコに関する情報がコントロールされていることに気がつかないのです。
—— 新型コロナウイルス感染症に関するインフォデミックにおいて,薬剤師が重要な役割を担えるのではないかと期待する声がありました。公衆衛生という視点から,薬剤師にできることはどのようなことでしょうか。
(田淵)新型コロナウイルス感染症の話に限定すると,陰謀論や科学的根拠のない情報がSNSなどを中心に氾濫しました。また,それは情報の出所が不明なものだけでなく,トランプ大統領などの政治家からも発信されています。
薬局は全国に約6万軒以上あり,コンビニよりも多いといわれています。また,診察のときにしか会えない医師と比べて,ふらっと薬局に立ち寄って話ができる薬剤師は,地域住民にとって最も身近な医療従事者といえます。したがって,薬剤師が「ワクチン接種の啓発」「感染症予防の指導」「正しい医薬品の使用に関する教育」などを行うことは公衆衛生の視点から非常に重要であり,薬剤師が果たせる役割は大きいと思います。次のパンデミックでは,薬局が地域の健康情報センターとして機能することが期待されます。
—— 今日はありがとうございました。最後に,薬剤師へのメッセージをお願いします。
(田淵)薬剤師の皆さんに期待するところはとても大きいです。というのは,地域住民に対する公衆衛生の最前線にあるのは薬局や保健所ですし,実際に接しているのは薬剤師の先生です。公衆衛生には,感染症対策だけでなく,タバコ問題,慢性疾患の管理,健康教育など,多くの課題があります。さまざまな公衆衛生分野において薬剤師の先生の活躍にとても期待しているので,今後も一緒に公衆衛生をより良いものにできればと思います。
| 引用文献 | |
| 1) | 古瀬祐気:新型コロナパンデミックの問題点と初期対応のエビデンス ─クラスター対策と予測数理モデルについて.調剤と情報,31(臨):180-186,2025 |