0からの
肥満症note
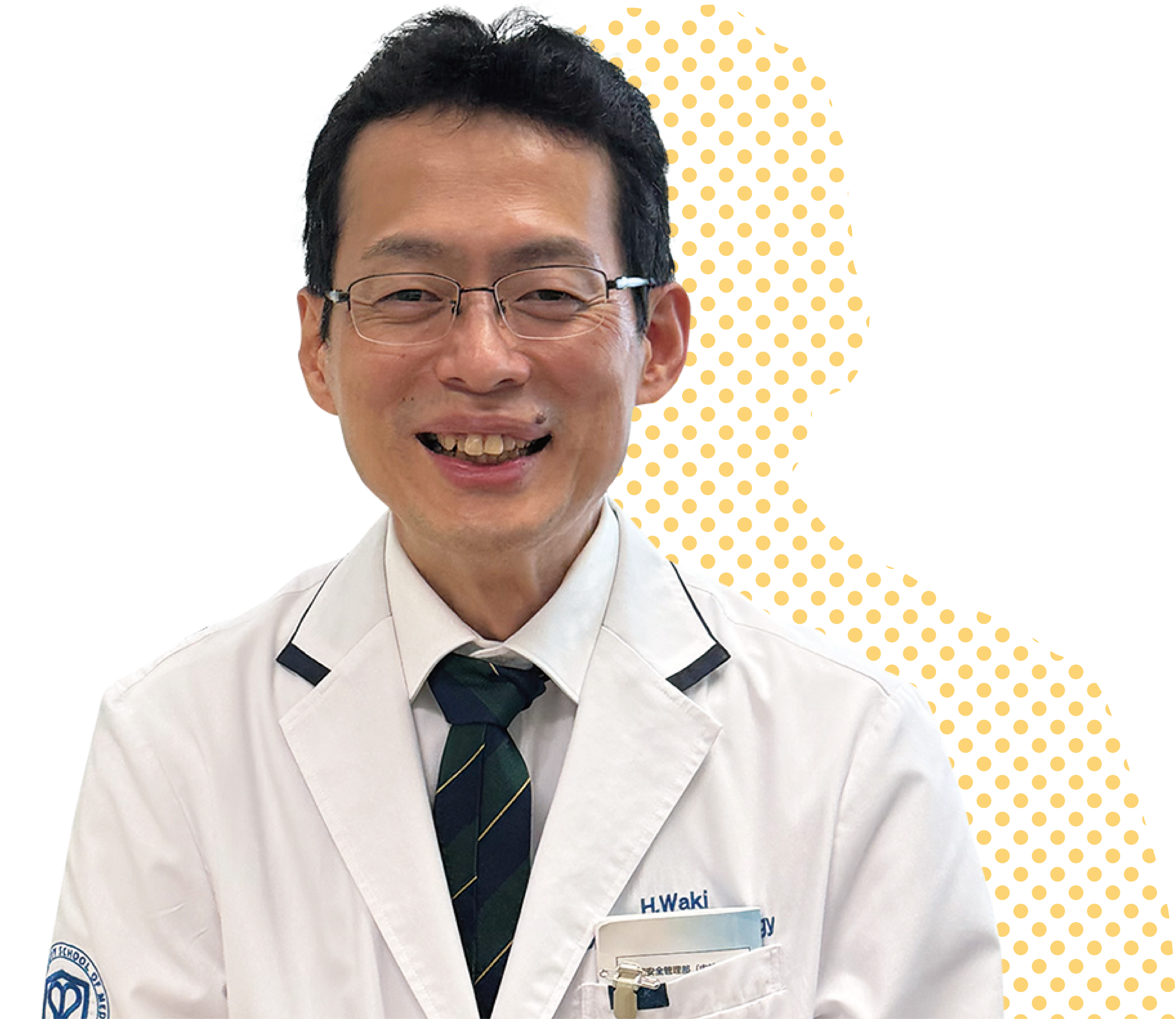
そこで「肥満症とは何か」をテーマに,本特集のオーガナイザーである秋田大学大学院医学系研究科の脇裕典 先生にうかがいます。
「肥満」と「肥満症」とは
—— 「肥満」と「肥満症」と2つの言葉を耳にしますが,違いはあるのでしょうか?
肥満とは,脂肪が過剰に蓄積した状態で,BMI〔体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)〕25(kg/㎡)以上の人に肥満があるとされています。ただし肥満がある人だとしても,すぐに健康障害を生じるわけではありません。
肥満のどこに問題があるかというと,さまざまな健康障害を合併しやすくなる点が挙げられます。具体的には,2型糖尿病,整形外科的な疾患(例:変形性膝関節症),月経異常,睡眠時無呼吸症候群など,多岐にわたる疾患が生じることが知られています。そして,こうした健康障害のうち1つでも合併している状態を「肥満症」と定義しています。これらの健康障害は肥満に起因あるいは関連しているため,減量することで改善が期待できます。
まとめると,肥満症は肥満に含まれる概念ですが,単なる肥満と区別して医療として減量が望まれる状態としての位置づけといえるでしょう。
なぜ尿酸値のコントロールが重要なのか
—— 肥満および肥満症の近年の傾向について教えてください。
日本人の2~3割程度にあたる約2,800万人が日本の肥満者数とされており,相当数の人に肥満があるといえます。他方,肥満症の患者数に関する具体的なデータはありませんが,肥満のある人の一定数が肥満症に該当すると考えられますので,かなりの患者数がいると推定されます。
近年の傾向として,特に男性の肥満のある人の人数が年代を問わず増加し続けてきましたが,ここ最近は横ばいに転じています。女性は減少傾向を示していますが,年代別にみると20代,30代,40代,50代,60代と年齢が上がるにつれて肥満者の割合が顕著に増加するため,中高年層では特に注意が必要です。
肥満・肥満症の問題点
—— 肥満および肥満症は,一般に生活習慣病と関連しているとされますが,実際にはどのような関連が指摘されているのでしょうか。
肥満に関連する健康障害のメカニズムとしては,インスリン抵抗性および脂肪組織の持続的な炎症が原因になると考えられています。慶應義塾大学の伊藤裕先生らが提唱したメタボリックドミノでは,肥満を起点として糖尿病や高血圧,脂質異常症などの生活習慣病を次々と発症し,それが心不全や脳卒中などの重大な疾患につながっていくことを示しています。
またこれらの代謝的要因とは別に,肥満のある人は体重による機械的負荷が大きいため,特に膝関節にダメージを負いやすく,変形性膝関節症などのリスクが高いとされます。また,睡眠時無呼吸症候群についても,肥満による気道閉塞が原因となるため,機械的要因による健康障害の一例といえます。

—— 近年,OTC 医薬品の販売や医療用医薬品の承認など,薬物治療という観点から肥満症治療の環境が大きく変化していますが,先生はどのように捉えていますでしょうか?
これまでの肥満症治療は,治療手段が限られているため生活習慣の改善が中心でした。そのため,十分な治療効果を得るためには,患者さんの並ならぬ努力が必要でした。それが近年,画期的な肥満症治療薬が登場したことにより,状況が大きく変わっています。
もちろん生活習慣の改善と薬物治療が,肥満症治療の両輪であることに変わりはありませんが,体重の減少がこれまでと比較して目に見えてわかるため,治療への意欲も向上し生活習慣の改善にも取り組みやすい1),そういった良い循環が生まれやすい状況になったのではないかと思います。
生活改善支援の例と効果
—— 肥満や肥満症の患者さんに対して,減量の目標はどのように考えればよいでしょうか。
特定保健指導の解析結果から,現体重から3%程度の減量ができれば,代謝異常や血圧高値などの改善が期待できることがわかっています。そのため,日本肥満学会も現体重からの3%減少(高度肥満症では5~10%減少)を目標として設定しています。
ここで,“現体重から”という点がポイントであることに触れておきたいと思います。減量の目標としてBMI22の理想体重と考えてしまいがちですが,BMI 25以上の人がBMI 22に減量するのは非常に高い目標です(例:身長179cmの人の場合,BMI 25のときの体重は約80kg,BMI 22のときは約70.5kg)。一方「現体重から3%程度の減量」であれば,80kgの人の場合は2.4kgの減量となるので,目標達成の現実味が増し,患者さんも取り組みやすくなるのではないかと思います。ただし,個人差があり3%減量したからといって誰しもが良くなるわけでなく,3%減量を達成しなくても良くなる人もいます。そのため,一律の数値目標よりも,その人にあわせた個別対応が重要です。
また,生活習慣における“行動変容”がまず大切なので,減量目標などの数値目標にとらわれず,患者さんの生活のなかで何から取り組めるのかについて,一緒に考えていくことが重要だと思います。
—— 生活習慣における行動変容に向けて,“何から取り組むのか”をどのように決めたらよいでしょうか。
生活習慣の改善の仕方は個人によって異なります。例えば,肉体労働の多い職場に勤務している人に「運動しましょう」としても効果が少ない可能性があるのは明らかですし,夜勤の多い人に「規則正しい生活を」といっても無理があります。したがって,運動・食事ともに重要であることは間違いありませんが,その人の生活スタイルにあわせて “何が良いのか”を一緒に考えることが重要なのです。
また,“何から取り組むのか”に迷ったときは,「調子の良かった時期の体重は? そのとき,何か頑張っていたことはありますか?」と聞いてみるのも効果的です。調子の良いときは,何かしら頑張っていたことがある患者さんがほとんどです。その“頑張っていたこと”が,上手くできなくなったために体重の増加につながっているため,そこに再びチャレンジするには何をどうしたらよいのかということを考えていくと,何に取り組むべきかがみえてくると思います。
肥満症の正しい知識をもつこととスティグマ
—— 「肥満は自己管理の問題」という偏見が根強いという話があります。この点についてどうお考えですか。
「肥満は自己管理ができていないから」という考え方は,確かに根強くあります。しかし,居住環境,職業,遺伝的要因など,さまざまな因子が肥満の発症に関わっており,必ずしも自己責任だけの問題ではありません。また,社会一般だけでなく医療従事者も,こうした偏見を無意識にもつことが指摘されています2)。
—— 医療従事者がスティグマを抱かないために,どのような視点が必要でしょうか。
医療従事者が抱くスティグマに関するある研究では,肥満のある患者と肥満のない患者に対する診療時間を比較すると,肥満のある患者の診療時間が明らかに短くなるということが報告されています2)。つまり,肥満がある患者に対し,医療従事者が無意識に「生活習慣がだらしないから」「運動をしていないから」といった決めつけや先入観をもっている可能性があるということです。
しかし実際には,生活習慣をしっかり管理していても肥満になってしまう患者もいれば,痩せていても生活が不規則という患者もいます。したがって,こうした決めつけを無意識にしてしまうことがあるんだ,生活習慣をきちんとしていても肥満となってしまう場合があるんだということを理解したうえで患者さんに接することが重要です。
—— 「肥満は自己管理の問題」という偏見が根強いという話があります。この点についてどうお考えですか。
「肥満は自己管理ができていないから」という考え方は,確かに根強くあります。しかし,居住環境,職業,遺伝的要因など,さまざまな因子が肥満の発症に関わっており,必ずしも自己責任だけの問題ではありません。また,社会一般だけでなく医療従事者も,こうした偏見を無意識にもつことが指摘されています2)。

—— 肥満のある患者への接し方や声かけの際に,配慮すべき点としてどのようなものがありますか?
肥満のある人は,幼少期からさまざまなスティグマを受けていることが多く,内向的で回避的な性格の人が多いとされています。つまり「批判されたくない」「そっとしておいてほしい」といった特性をもっている可能性が高いといえます。したがって,肥満のある患者さんには,こうした背景を理解したうえで言葉選びや接し方に配慮する必要があるでしょう。
例えば,体重が減少している時は積極的に評価し,体重が増えてしまった場合には「それでも継続して通院されているのは素晴らしいこと」と温かく迎えることが継続した治療を行ううえで大切です。また,そもそも体重の話題を持ち出すことに抵抗がある人もいます。そのような細やかな配慮が必要だと思います。
薬剤師に期待される役割
—— 肥満症の予防・治療において,薬局・薬剤師に期待される役割はどのような点にあるでしょうか。
オルリスタットは OTC 医薬品として販売されており,薬局やドラッグストアでの対応が中心となります。したがって,服薬をリードする立場にあるのは薬剤師です。また,3カ月間の継続的な生活習慣指導が義務となっていますが,これも薬剤師が担当することとされており非常に重要な役割を担っているといえます。
GLP-1 受容体や GIP 受容体の作動薬などの医療用医薬品に関しては,病院やクリニックで処方されますが,薬物療法が治療の大きな柱となった現在,副作用への注意や注射の適切な使用方法など,専門的な支援が求められており,薬剤師の役割は大きいといえるでしょう。
また,肥満症に限った話ではありませんが,診察室で医師には遠慮してさまざまな悩みを話してくれない患者さんも少なくありません。そうした話が薬剤師にはできるという患者さんもいるので,患者さんに近い立場で情報を収集し,医師との橋渡し役を担っていただくことも期待されます。
—— 最後に,読者へのメッセージをお願いします。
肥満症治療の環境が大きく変化している現在,薬剤師には正しい知識を身につけ,偏見やスティグマをもたずに患者さんに接していただきたいと思います。特に,肥満症を予防する,健康を支援するという領域では薬剤師が主役となる場面も多くなっています。患者さん一人ひとりの生活に寄り添いながら,継続的な支援をお願いできればと思います。
| 引用文献 | |
| 1) | Kato S, et al: Impact of Tirzepatide on diet-related quality of life and treatment satisfaction in people with type 2 diabetes mellitus: a retrospective cross-sectional study. Diabetes Res Clin Pract, 229: 112913, 2025 |
| 2) | Rubino F, et al: Joint international consensus statement for ending stigma of obesity. Nat Med, 26: 485-497, 2020 |
脇 裕典
秋田大学大学院医学系研究科 代謝・内分泌内科学講座 教授。脂肪細胞のエピゲノム制御と肥満症・糖尿病との関連を解明する研究で日本医師会医学研究奨励賞をはじめ複数の学術賞を受賞。代謝・内分泌疾患の専門家として診療ガイドライン策定や学会活動にも積極的に参画し,現在は秋田県における糖尿病重症化予防プロジェクトを推進している。基礎研究の知見を臨床に還元しつつ,地域に根ざした医療の実践に取り組んでいる。