高尿酸血症の予後と
ライフスタイル改善が
もたらすこと
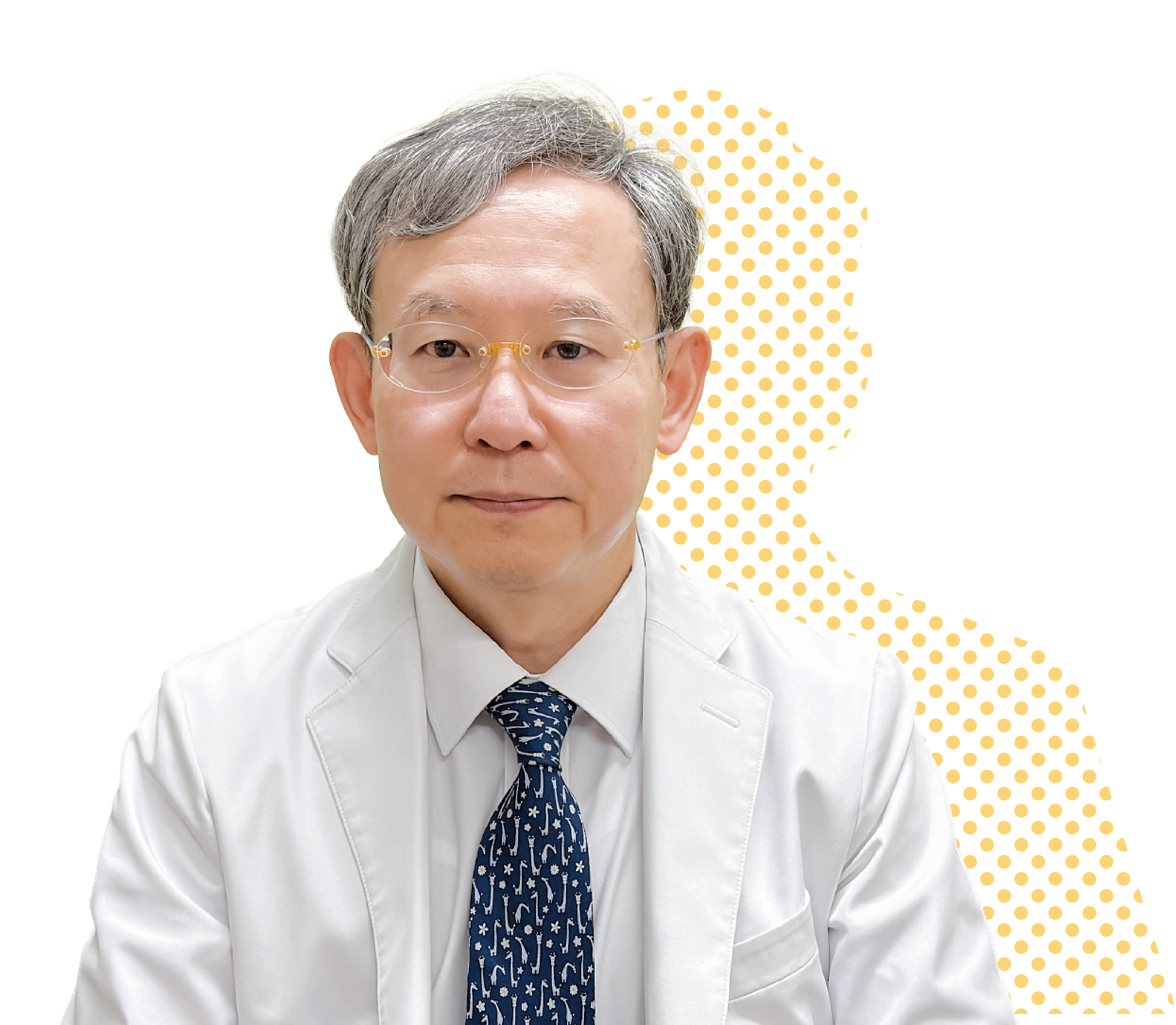
福井大学医学部の山内高弘先生に、最新の知見と薬局での役割について伺いました。
高尿酸血症と痛風の近年の動向
—— 高尿酸血症および痛風の昨今の動向はどのようになっているのでしょうか?
かつて日本には,痛風という病気はほとんどみられませんでした。安土桃山時代に来日したポルトガル人宣教師ルイス・フロイスは「日本人には痛風がない」と記しており,明治時代初期に滞在していたドイツ人医師ベルツ博士も「日本には痛風患者がいない」と述べています。実際に日本で痛風が確認されるようになったのは,戦後,1960 年代以降のことです。
現在では,日本人成人における高尿酸血症の割合は,特に男性で約3割にのぼります。これに伴い,痛風の有病率も増加しており,成人男性の 1 〜1.5%が発症していると報告されています。高尿酸血症・痛風はいずれも男性に多く,特に痛風は,その 98.5%を男性が占めているというデータもあります。また,年齢層は30〜70代までと幅広いです。
このような状況の背景には,遺伝的要因に加えて食生活の欧米化や肥満の増加,運動不足といった生活習慣の変化が影響していると考えられています。
なぜ尿酸値のコントロールが重要なのか
—— 尿酸が高値だと,なぜ身体に悪影響を及ぼすのでしょうか? 一方で,尿酸値が低すぎるのも問題になるとされますが,尿酸は身体のなかでどのような役割を担っているのでしょうか?
尿酸は,もともと体内で抗酸化物質として働くことが知られており,特に活性酸素を除去する作用をもつことから,生理的な範囲内であれば一定の機能的意義があると考えられています。しかしながら,現代のように栄養状態が非常に良好で,肉類や果糖を多く含む清涼飲料水,アルコールなどの摂取量が増えている環境では,プリン体の摂取が過剰になりやすい状況といえます。プリン体は体内で最終的に尿酸に変換されるため,摂取量が多くなるほど血中の尿酸値も上昇しやすくなります。さらに,遺伝的に尿酸トランスポーター1(URAT1)の機能が強く,尿酸をより多く再吸収してしまうために,尿中への排泄が少なく,尿酸値が上がりやすい人が一定数います。こうした人においては,現代の生活水準では,尿酸値が顕著に上昇しやすい状況であるといえます。
また,体温が相対的に低い足の指の関節などに沈着した尿酸の結晶が,何らかの誘因で関節腔内に遊離すると,白血球がそれを貪食し,激しい炎症反応を引き起こし痛風発作となるわけです。さらに近年では,痛風発作を発症しないぐらいの値でも,慢性的に持続することで血管内皮を障害することがあります。これは腎障害や高血圧などに関連しているのではないかと示唆されており,現在も研究が進められています。
一方,尿酸値が極端に低い場合も注意が必要です。まれではありますが,尿酸降下薬が効き過ぎると低尿酸血症となる場合があります。もし3.0mg/dLを切るような患者をみかけた場合は専門医への受診を勧奨していただければと思います。
このように,尿酸は高すぎても低すぎても身体にとって負担となり得るため,適正な範囲で維持することが大切であるといえます。
高尿酸血症と生活習慣病との関連

—— 高尿酸血症は無症状のことが多く,無治療やコントロール不良となる患者も少なくありません。このような患者の場合,痛風発作や腎障害などのリスクが思い浮かびますが,近年では生活習慣病との関連も示唆されています。具体的にはどのような疾患との関連が指摘されているのでしょうか? また,薬剤師が患者と接するなかで留意すべき点などがあればあわせて教えてください。
高尿酸血症は,痛風や腎障害だけでなく,近年では高血圧,糖尿病,脂質異常症,メタボリックシンドロームといった生活習慣病との関連が示唆されています。多くの患者では,このいずれかの生活習慣病を併発していることが多く,高尿酸血症を単独で罹患している患者は全体の2割程度とされています。
生活習慣病が先か高尿酸血症が先かという議論はあるものの,疫学的にみると,例えば高尿酸血症の患者が高血圧を併発していることが多いということが確認されています。なお,明確な理由の解明には至っていませんが,前述のとおり尿酸が血管内皮を障害するなどの理由が考えられており,今後の研究が待たれます。
患者と接する際には,「痛風の既往がないから」という認識ではなく,無症候性であっても他の生活習慣のリスク因子となる可能性があるという視点が重要です。したがって,服薬指導や健康相談のなかで,生活習慣へのアドバイスを丁寧に行い,必要に応じて医師への橋渡し役としての役割が求められます。特に尿酸値が高く,なおかつ高血圧や糖尿病などを併発している場合は,積極的にそのリスクを認識してもらうための声かけが重要になるでしょう。
高尿酸血症の経過とリスク
—— 高尿酸血症を無治療で放置した場合,一般的にどのような経過を辿ると考えられますか?
無症候性高尿酸血症の場合,保険制度の違いもありますが,欧米では原則として薬物治療の対象とはなりません。日本では,一定の尿酸値以上であれば積極的に治療介入が検討されます。尿酸値を適切な濃度にコントロールすることで,確実に痛風発作のリスクを抑えることが可能であり,生活習慣病との関連からも治療介入は適切であろうと思います。
なお,無治療のまま放置した場合に,まず懸念されるのはやはり痛風です。血清尿酸値が高い状態が続くことで,関節に尿酸の結晶が沈着し,発作性の関節炎を引き起こすようになります。これを繰り返すことで,結晶が関節周囲に慢性的に蓄積し,いわゆる痛風結節が形成され,最終的には関節破壊に至ることもあります。
実際の臨床でも,特に若年層において高尿酸血症の存在に気づかないまま過ごし,ある日突然,初発の痛風発作をきっかけに外来を受診される方が少なくありません。この段階では強い痛みを伴いますが,発作はおおむね1〜2週間で自然に軽快し,いったんはおさまるケースが多くみられます。しかし,このタイミングで痛風の診断がついても,症状がなくなると薬剤の必要性を実感しにくくなり,尿酸降下薬の服用を自己中断してしまう患者も一定数います。そうした患者は,いずれ再度の痛風発作を繰り返すことになり,結果的に関節障害や生活の質の低下を招いてしまう可能性があるのです。したがって,発作が一度治まった後も,継続的な管理と治療継続の重要性についてしっかり理解を促し,フォローアップを行っていくことが大切です。
高尿酸血症の経過とリスク

—— 本特集では,「ライフスタイルの改善」に注目しています。ライフスタイルの改善により,期待される効果や,薬局・薬剤師の介入が患者の行動変容に結びついた例などがあれば教えてください。
高尿酸血症に対するライフスタイルの改善は,『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版』で明確に推奨されており,基本となるのは,「食事」「アルコール摂取量の調整」「運動」の3点です。
「食事」においては,カロリーの過剰摂取を避けるとともに,プリン体の摂取量を抑えることが重要です。近年では,DASH食や地中海食のように,野菜・果物・ナッツを中心としたバランスの取れた食事パターンが,高尿酸血症の管理にも有用とされています。また,「アルコール」についても過度の摂取は尿酸値を上昇させる要因になるため,量と頻度のコントロールが求められます。
「運動」については,有酸素運動を中心に取り入れることが勧められます。なお,無酸素運動では乳酸が産生されることで尿酸の排泄が抑制され,結果的に血中尿酸値が上昇する可能性があるため,避けたほうがよいとされています。
高尿酸血症は,単独の疾患としてだけでなく,メタボリックシンドロームの周辺疾患として捉えることもできます。そのため,体重や血圧,コレステロールなど,他の生活習慣病リスクも同時に管理していく必要がある患者が少なくありません。単に尿酸値を下げるという目標だけでなく,生活習慣全体を総合的に見直していくことの重要性を,薬剤師が丁寧に伝えていくことが求められます。
実際の薬局の現場では,「数値が高いので薬を飲みましょう」という一方的な提案だけではなく,「なぜ生活を見直す必要があるのか」「どこから取り組めばよいのか」といった点を患者自身が理解し,納得できるようなコミュニケーションが大切です。例えば,清涼飲料水や間食が多い若年男性に対して,日常的な飲み物の選択肢を一緒に考えるだけでも,行動変容のきっかけになることがあります。小さな改善の積み重ねが,将来的な薬物治療の必要性を減らす可能性もあるという視点を,薬剤師が積極的に伝えていけるとよいと思います。
治療継続のカギは薬剤師にある
—— 最後に,薬剤師に期待すること,または日常業務のなかで高尿酸血症にどう向き合ってほしいか,メッセージをお願いします。
痛風発作は強い痛みを伴うため,発作時には多くの患者が医療機関を受診しますが,発作が治まってしまうと,その後の通院や服薬が中断されてしまうケースも少なくありません。結果として,無症状の高尿酸血症のまま放置され,再発や合併症を引き起こしてしまうリスクが高まります。
こうした背景を踏まえ,薬剤師の皆さんには,痛風や高尿酸血症の病態をきちんと理解したうえで,服薬継続の重要性を患者に丁寧に伝えていただきたいと思います。特に無症状の時期こそが,治療を継続して将来的なリスクを減らすチャンスであることを,わかりやすく説明していただけるとありがたいです。
薬剤師の皆さんが日常業務のなかで,患者の理解や行動変容を後押ししてくださることを大いに期待しています。
山内 高弘
福井大学医学部(旧 福井医科大学)卒業後、米国 MD Anderson で抗がん薬研究に従事。臨床薬理・がん化学療法、痛風・高尿酸血症の専門家としてガイドラインや学会運営にも携わる。現在は血液・腫瘍内科長、副病院長などを兼任。「楽しく、仲良く、全力で!」をモットーに、地域住民の健康を支える診療と医療水準の向上に尽力するリーダーである。