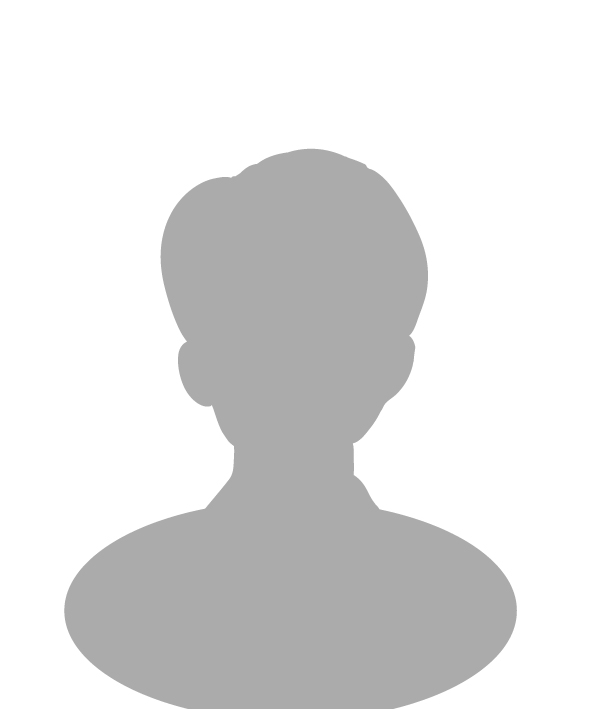第58回日本薬剤師会学術大会 分科会14レポート
第58回日本薬剤師会学術大会 分科会14レポート
薬剤師が栄養管理に関わる意義

日本の高齢者の栄養状態は深刻な課題を抱えている。要介護4~5の高齢者の半数以上が低栄養または低栄養リスクを有しており,適切な栄養管理の有無が生命予後を大きく左右する。この現状を打破するため,薬剤師の栄養管理への参画が強く求められている。
2025年10月12日・13日,国立京都国際会館で開催された第58回日本薬剤師会学術大会の分科会14「薬剤師による栄養管理の関わり」では,この課題に対する具体的な解決策が議論された。座長を務めた日本薬剤師会理事の池田里江子 氏と京都府薬剤師会理事の金山美沙 氏は,「栄養士や医師に任せるのではなく,薬剤師としての視点で考え,他職種と連携することが必要」と述べ,栄養の視点を持った薬剤師を増やすことの重要性を強調した。
登壇したのは,ちゅうざん病院 副院長の吉田貞夫氏,浅ノ川総合病院 薬剤部主任の東敬一朗氏,若葉薬局の豊田義貞氏の3名。それぞれ医師,病院薬剤師,薬局薬剤師の立場から,栄養管理における薬剤師の役割と実践について講演が行われた。
 栄養管理を行う際に,医師の立場から薬剤師のみなさんにお願いしたいこと
栄養管理を行う際に,医師の立場から薬剤師のみなさんにお願いしたいこと
吉田氏は冒頭,医療・介護を支える3つのインフラとして「感染対策」「栄養管理」「リスクマネジメント」を挙げ,これらがなければ医療介護は成り立たないと強調した。特に超高齢社会における栄養アセスメントの重要性を指摘し,高齢者のための栄養評価ツールであるMNA(Mini Nutritional Assessment)を紹介した。
MNAによる栄養評価と生存率の関連
MNAは6項目で評価を行い,慣れれば1~2分で評価が可能な簡便なツールである。吉田氏は,MNAを用いた研究結果を示しながら,「栄養状態良好と判定された人の3年後の生存率は80%であったのに対し,低栄養と判定された人は20%を切る」と述べ,栄養状態が生命予後に直結することを強調した。
さらに,要介護4~5の利用者では半数以上が低栄養または低栄養リスクに該当するというデータを示し,「要介護4~5の方がいらっしゃったら,何か栄養の問題を抱えているに違いないと考えていただきたい」と訴えた。
薬局での栄養スクリーニングの可能性
吉田氏は薬局薬剤師への具体的な提案として,待ち時間を利用したMNA実施を挙げた。「待ち時間に用紙を記入していただき,低栄養や低栄養リスクと判定された場合は,主治医や訪問看護師などに一言声をかけていただくだけでも,栄養ケアのきっかけになる」と述べた。これがチーム医療への参画の入り口になり,薬剤師が総合的・全人的な服薬管理を目指すうえでの重要なツールになると位置づけた。
GLIM基準による低栄養診断
さらに吉田氏は,低栄養の診断基準として世界共通で作成されたGLIM基準(国際的な低栄養診断基準)を紹介した。GLIM基準はMNAと異なり,「病名として低栄養をつける」ことを目的としており,「診断をしたら適切なケアを行う義務が生じる」と指摘した。
GLIM基準では,表現型(体重減少,低BMI,骨格筋量減少)と病因(食事量減少,消化吸収異常,疾患による炎症)の各項目から1項目以上が該当すると低栄養と診断される。吉田氏は,「回復期リハビリテーション病棟ではGLIMを使わないと診療報酬が認められなくなった。今後,在宅でもGLIM導入が求められる可能性がある」と述べ,早めの準備を呼びかけた。
サルコペニア・フレイルへの対応
高齢者の課題としてサルコペニア(加齢性筋肉減少症)を取り上げ,CT画像で一般成人と高齢者の筋肉量を比較して示した吉田氏は,「筋肉はタンパク質の貯蔵庫であり,栄養状態が悪くなると筋肉のタンパク質がエネルギーとして利用される。低栄養を防ぐことでサルコペニアの進行を遅らせることができる」と,栄養管理の重要性を解説した。
チーム医療における薬剤師の専門性
吉田氏は薬剤師の強みとして,生化学的知識を挙げた。「薬剤師はクエン酸回路やビタミンB₁不足による代謝への影響など,生化学が得意。これは他職種が苦手とする分野」と述べ,葉酸サイクルやメチオニンサイクルを「メチル基のバケツリレー」としてわかりやすく説明できる専門性を強調した。
また,栄養サポートチーム(NST)への参加を促進するため,食欲低下や嚥下障害に関連する薬剤の定型コメントを電子カルテに準備し,簡便に参加できる仕組みを紹介した。
 薬剤師が栄養管理に関わる意義ともたらされる未来―栄養沼にはまった病院薬剤師からのメッセージ
薬剤師が栄養管理に関わる意義ともたらされる未来―栄養沼にはまった病院薬剤師からのメッセージ
東氏は,最初は上司命令で嫌々始めた栄養管理に20年以上取り組んできた経験を語った。「栄養の知識を持つと薬剤師としてのスキルが上がる」と強調し,薬以外の要因(脱水,炎症,栄養状態など)も含めて総合的に患者の状態を評価できるようになることの重要性を訴えた。
経腸栄養剤と静脈栄養の本質的な違い
東氏は経腸栄養剤と静脈栄養の違いを,「コンビニ弁当」と「食材」に例えて説明した。経腸栄養剤は栄養バランスが考えられており,「よほど変なものを選ばない限り,しばらく摂取しても問題が起きない」のに対し,静脈栄養は「食材」であり,「ちゃんと選択して組み合わせて調理して初めて食事に相当する」と指摘した。
「薬剤師は静脈栄養に関しては三ツ星シェフでなければならない」と述べ,薬剤師の専門性発揮を求めた。
「健康な人の静脈栄養」を考える重要性
東氏は参加者に対し,「健康な人の静脈栄養を考えたことがあるか」と問いかけた。「健康な人は静脈栄養が必要ないという矛盾をはらんでいるが,健康な人の静脈栄養ができない人が,病気を持った人の静脈栄養ができるとは思えない」と述べ,まず自分自身を例に,必要エネルギー量とアミノ酸量を決めて輸液処方を組み立てる演習を提案した。
誤嚥性肺炎患者への不適切な栄養管理
東氏は衝撃的な事実として,静脈栄養のみで管理されていた患者のエネルギー投与量は体重1kgあたり8.7kcal,アミノ酸投与量は0.38gと,ガイドラインで求められる量の3分の1程度であり,脂質投与量の中央値は0だったと報告した。
「これを食事に置き換えると,栗ご飯,納豆,水だけで1カ月過ごすようなもの。誤嚥するほど栄養状態が悪い人に,このような栄養管理では食べられるようになるはずがない」と厳しく指摘。医療が「嚥下機能低下を後押しして食べられない高齢者を作る工場」になっている側面があると警鐘を鳴らした。
コモンセンスベースドニュートリション
東氏は「コモンセンスベースドニュートリション(一般的な感覚に基づいた栄養療法)」という造語を紹介した。「毎日焼肉ばかり食べないし,スポーツ飲料だけで生きていけない。まったく脂質を含まない食事を取ったこともない,これらはあたり前のこと」と述べ,この当たり前を患者に提供することの重要性を強調した。
「一般的な感覚が欠落している人が使うエビデンスは時として凶器になる」と警告した。
マルチバッグ製剤の落とし穴
高カロリー輸液のマルチバッグ製剤について,「オールインワンで優れた製剤に見えるが,実はバランスが悪い」と指摘した。添付文書どおりの1日2本使用ではアミノ酸量は適切だがブドウ糖が多すぎる。一方,1本使用ではブドウ糖量は適切だがアミノ酸が不足する。
そのため「NSTではマルチバッグ1本にアミノ酸製剤を追加する処方を組む」と実践的なアドバイスを行った。
嚥下機能に影響する薬剤への注意
東氏は,嚥下機能に影響する薬剤,特に抗コリン薬の問題を取り上げた。「抗コリン作用により唾液が出なくなると,食塊形成(食べ物を飲み込みやすい塊にまとめること)のつなぎとして必要な唾液がなくなり飲み込めなくなる。また,味の成分は唾液に溶けて味覚細胞に到達するため,唾液がないと味を感じない」と説明した。
味覚障害に対して反射的に亜鉛補充を考えがちだが,「唾液が不足しているために味を感じない人に,亜鉛を補充しても味覚は改善しない。まず口腔内を確認し,乾燥していれば抗コリン作用のある薬剤を服用していないかを確認することが重要」と述べた。
健康寿命と平均寿命の乖離を縮める
東氏は,男性で8~9年,女性で約12年ある健康寿命と平均寿命の乖離がこの20年間縮まっていないことを指摘。「誤嚥性肺炎患者への不適切な栄養管理と,食事に影響する薬剤が症状改善後もダラダラ続いている状況では,この乖離が縮まるはずがない。これらは薬剤師ができることが多い領域」と述べ,薬剤師が職能を発揮することで健康寿命の延伸に貢献できると強調した。
 薬局薬剤師が地域で実践する栄養学的支援―薬学管理の質を高める「隠し味」
薬局薬剤師が地域で実践する栄養学的支援―薬学管理の質を高める「隠し味」
豊田氏は在宅栄養支援の実践について語り,「栄養支援は共通の目標で横断的介入が可能であり,誰もが何らかのかたちで関われる。もちろん薬剤師も」と述べ,多職種連携における薬剤師の位置づけを明確にした。
薬局でのMNA調査と体重測定の重要性
豊田氏は過去に自身の薬局で実施したMNA調査を紹介した。65歳以上の来局患者100名を対象に実施した結果,「全体の半数以上の患者が自分の体重を知らない」という実態が明らかになった。特に低栄養リスク群や低栄養群ではほとんどの人が体重を把握していなかったという。
この結果を受けて薬局に体重計を設置し,継続的な体重測定を促す取り組みにつながったと報告した。
また,MNAの代わりに日常的に聴取できる5つの項目を提案した。「3食摂れていますか,調理していますか,買い物に行けていますか,歯はありますか,誰と食べていますか―このなかで一つでも問題があれば,食生活をより深く確認するようにしている」と述べ,実践的なスクリーニング手法を示した。
薬局薬剤師が担う7つの役割
豊田氏は薬局薬剤師が在宅栄養支援で担うべき役割として7項目を提示した。
「薬局ほどスクリーニングに適した場所はない」と強調し,薬剤師が栄養支援の入り口として機能することの重要性を訴えた。また,「栄養療法は全ての職種が関われるため,チーム医療の経験を積みたいのであれば,入り口として非常にやりやすい」と述べ,栄養を切り口とした多職種連携の可能性を示した。
 分科会総括と質疑応答から見えた薬剤師の課題と可能性
分科会総括と質疑応答から見えた薬剤師の課題と可能性
本分科会では,栄養管理における薬剤師の役割が多角的に示された。MNAやGLIM基準といった具体的なツールの活用,薬局でのスクリーニング機能,生化学的知識を活かした専門性の発揮,静脈栄養の適正化,嚥下機能に影響する薬剤への注意,そして多職種連携におけるつなぎ手としての役割―これらを通じて,薬剤師が栄養管理に関わることで患者のQOL向上と健康寿命の延伸に貢献できることが明らかになった。
質疑応答では,管理栄養士との役割分担について質問が挙がった。これに対し豊田氏は,「薬剤師が栄養に取り組むことが前提。管理栄養士との連携はその後の話」と述べ,まず薬剤師自身が栄養の知識を持ち,患者の生活に目を向けることの重要性を強調した。「専門職としての力を高めないと多職種連携はできない。栄養に興味がないまま管理栄養士を雇っても,お互いが不幸になる」と厳しく指摘した。
吉田氏は国際的な視点から,「日本は食事を管轄する省庁と薬を管轄する厚生労働省が異なるが,アメリカではFDA(米国食品医薬品局)が両方を管轄し,薬剤師と管理栄養士が業務を重ねながら協働している」と述べ,互いの専門性を理解し合うことの重要性を指摘した。
東氏は病院での経験から,「お互いのことを知らないと連携できない。知識のオーバーラップと共通言語化が重要」と述べ,栄養士の業務にも薬剤師が意見を述べ,逆に栄養士からも薬剤の提案を受けるような双方向の関係性を示した。
NST専門療法士の資格について,東氏は「資格を取ることを目標にするのではなく,実践した結果として資格がついてくるぐらいの考えでよい」と述べた。一方で,豊田氏は「薬剤師はNST専門療法士の合格率がダントツで高い。生化学を専攻している職種は薬剤師ぐらいで,薬学と栄養学は非常にオーバーラップしている」と,薬剤師の適性を強調した。
「栄養に興味を持つこと」「自ら学ぶこと」「患者の生活に目を向けること」の重要性が繰り返し強調された本分科会。栄養支援はすべての職種が関われる横断的な領域であり,チーム医療の入り口として薬剤師の参画が期待されている。東氏が述べた「薬物療法にはもっと生活の視点が必要」という言葉は,これからの薬剤師に求められる姿勢を端的に表している。