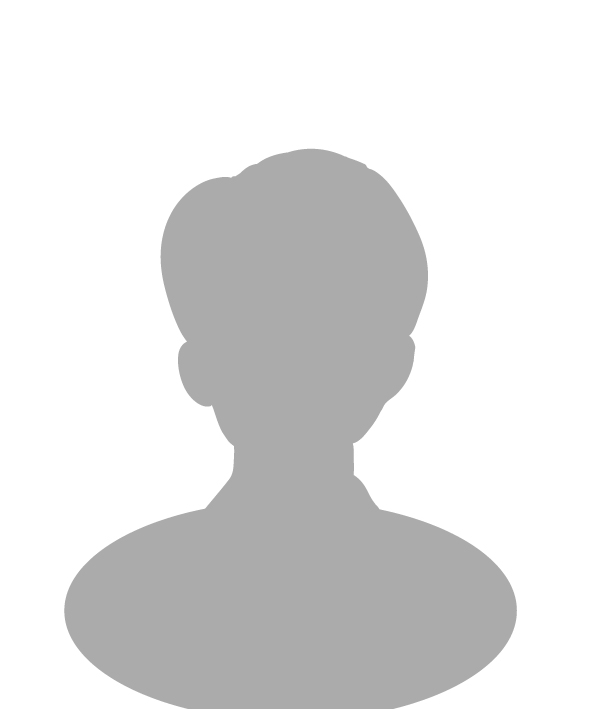国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター メディアセミナー
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター メディアセミナー
AMR対策における薬剤師の役割─患者説明の実践的アプローチ

2025年10月1日,国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センターは「AMR対策の最新の取り組み」と題したメディアセミナーを開催した。薬剤耐性はサイレントパンデミックともよばれ,感染症の流行と同様に社会に大きな影響を及ぼすとされている。2016年に発表された報告書によると,2050年には薬剤耐性によって年間1,000万人が死亡するとされており,がんによる死亡者数を上回ると指摘している1)。現在の日本においても,年間9,000人以上が薬剤耐性菌を原因に死亡していると推計されており,薬剤耐性(AMR)対策は喫緊の課題である2)。
薬局薬剤師は,AMRの啓発・患者教育という点において重要な役割を担っていることは明らかであるが,患者の理解が進んでいないという指摘もされており,さらなる取り組みが求められている。本稿では藤友結実子氏(AMR臨床リファレンスセンター 情報・教育支援室長)が行った「AMRに関する教育啓発活動の現状」と題した講演の内容を踏まえ,薬剤師が患者に対してどのように説明すべきかを考察したい。
 テーマは「かぜに抗菌薬は効きません」
テーマは「かぜに抗菌薬は効きません」
2025年度のAMR対策推進月間のテーマは「かぜに抗菌薬は効きません」である。いわゆる風邪症状の多くはウイルスが原因であり,抗菌薬の標的部位である細胞壁やリボソームなどの構造はウイルスには存在しないため,一般に風邪症状には無効である。しかし,抗菌薬が感冒に対して使用されている例がまだまだ少なくないのが現状である。無効であるだけであればまだしも,抗菌薬による副作用のリスクは無視すべきではなく,抗菌薬を使用すれば耐性菌の発生リスクが生じることから,個人レベルでも,社会レベルでも,不適切な抗菌薬使用は不利益しかない。実際に,MRSA菌血症とフルオロキノロン耐性大腸菌血症で2023年に国内で9,000名以上が死亡したと推計されており,2022年の交通事故死亡者数が2,610名であったということを考えるとAMR対策が喫緊の課題であることが理解できる2),3)。
 薬剤耐性が生まれるメカニズム
薬剤耐性が生まれるメカニズム
細菌は「外膜を変化させて薬剤の透過性を低下させる」「排出ポンプによる薬剤排出」「β-ラクタマーゼなどの酵素を産生して抗菌薬を分解」「薬剤の標的部位の構造を変化させて効かなくする」など,多様な耐性メカニズムで薬剤耐性を獲得する。また,この薬剤耐性菌は病原菌に限った話ではなく,皮膚や腸管に存在する常在菌も同様に薬剤耐性を獲得するのである。常在菌であれば,薬剤耐性を獲得しても問題とならないと考えられるかもしれないが,がん治療中の患者や免疫抑制薬を使用している患者などでは,日和見感染により命を落としかねないのである。また,自分だけでなく便や分泌物などを介して他者に伝播する可能性もある。
 患者の誤解にどう向き合うか
患者の誤解にどう向き合うか
不適切な抗菌薬の使用が不利益となることは明らかであるが,「抗菌薬意識調査レポート2023」 4) では,抗菌薬に対し正しい知識をもっている一般の人は約1/4に過ぎないと報告されている。
先日,社会保険診療報酬支払基金から感冒に対する抗生物質の算定は原則として認められないという通知 5) が出されたが,ソーシャルメディアでは「抗菌薬は風邪に効かないと言われて処方されなかったが全然良くならず,抗菌薬をもらったら良くなった」「最初から抗菌薬を処方してくれればよかったのに」「抗菌薬を飲まなかったから重症化したと思う」などといった投稿が散見された。また,診察室でも「自分の風邪には抗菌薬が効く」と主張する患者も存在し,患者の誤解をどう解消し,不適切な抗菌薬使用を是正していくかがポイントとなる。
症状の自然経過と抗菌薬服用のタイミング
患者が「抗菌薬が効いた」と感じる理由の一つは,症状が良くなるタイミングと抗菌薬服用のタイミングが重なりやすいことにある。風邪症状は一般的に,発症後2~3日で発熱のピークを迎え徐々に快方に向かっていくことが多い。そして,多くの患者の受診タイミングは,発症直後ではなく通常,翌日または翌々日である。つまり,症状のピークと受診のタイミングが重なるのである。
したがって,受診しようがしまいが自然経過として症状は快方に向かっていくのであるが,患者は処方薬を飲んだから風邪が治ったと勘違いしてしまうのである。この服薬タイミングと自然経過がたまたま重なることによる誤解であるということを,あらかじめ患者に説明しておくことが必要であろう。
ただし,AMR対策は適切な抗菌薬の使用を制限するものではない。「風邪に抗菌薬は不要」一辺倒では,患者も納得しにくい部分があるため「熱は2~3日で下がってくれば抗菌薬は不要です」「下がらない場合は風邪でない可能性があるため抗菌薬を服用します」「不要な抗菌薬を服用することは,不要な副作用に苦しむリスクを高めます」といった情報を提供し,患者の判断材料を確保することが重要である。
重症化予防効果のエビデンス
感冒に対して抗菌薬を12,255回処方すると,入院が必要となるような肺炎を1例のみ防ぐことができるという報告がある6)。また,上気道感染症の合併症である副鼻腔炎や急性中耳炎,中耳炎後の乳突蜂巣炎に対する抗菌薬の予防効果は,4,000人に1人で効果が認められると示されている7)。1/10,000は,宝くじで100万円が当選する確率と同じ程度であることからわかるように,期待できる効果は非常に小さいことがわかる。
しかしながら,患者にとっては「肺炎を防げる可能性が少しでもあるなら試したい」と思うことは至極当然である。この点を理解し,「風邪でないときの対応」や「副作用リスクの確率のほうが十分高いこと」など,多面的な情報提供をする必要があるだろう。
 おわりに
おわりに
「風邪に抗菌薬は不要」と患者に伝えることだけで,AMR対策は達成されない。患者の誤解の背景を理解し,「症状の自然経過」「風邪でないときの対応」など,必要な知識と症状経過から考えられる対応について説明し,患者の不安を取り除くことが必要なのではないかと考えられる。また,抗菌薬をはじめ患者は副作用リスクを過小評価する場合も少なくない。期待される薬効と副作用リスクを天秤にかけ,「期待される薬効がリスクを上回るから処方されているんだ」「期待される薬効が小さいから処方されないんだ」ということを丁寧に説明していくことが求められている。
前述のとおり,交通事故で亡くなる人よりも薬剤耐性菌によって亡くなる人のほうが大きく上回ると推計されている。薬剤耐性の問題は確実に深刻化しており,一人ひとりの薬剤師が日々の調剤業務のなかで適正使用を推進していくことが,この問題の解決につながっていく。
患者との対話のなかで,科学的根拠に基づいた説明と,個々の患者の状況に応じた配慮を両立させること。それこそが,AMR対策領域で薬剤師に求められている。
引用文献
- O'Neill J:Tackling Drug-Resistant Infections Globally:Final Report and Recommendations.The Review on Antimicrobial Resistance,2016
- 薬剤耐性ワンヘルス動向調査検討会:薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書2024.2024
- 警察庁交通局:令和4年中の交通事故死者数について(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/050302R04nenkan.pdf)
- 国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター:抗菌薬意識調査レポート2023(https://amr.jihs.go.jp/pdf/20231026_report.pdf)
- 社会保険診療報酬支払基金「651 抗生物質製剤又は合成抗菌薬【内服薬】(感冒等)の算定について」(令和7年8月29日)
- Meropol SB,et al:Risks and benefits associated with antibiotic use for acute respiratory infections:a cohort study.Ann Fam Med,11:165-172,2013
- Petersen I,et al:Protective effect of antibiotics against serious complications of common respiratory tract infections:retrospective cohort study with the UK General Practice Research Database.BMJ,335:982,2007