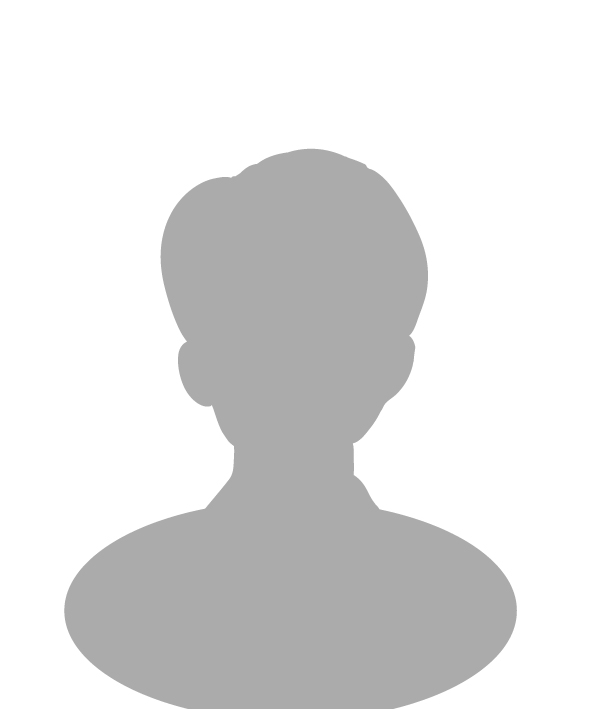日本社会薬学会第43年会 レポート

2025年9月6日〜7日,日本社会薬学会第43年会が和歌山県立医科大学薬学部(和歌山市)で開催された。大会スローガンは「Uplifting the Whole People!薬剤師による社会・公衆衛生への貢献」。薬剤師が社会に果たす役割を見直し,広げていくことをテーマとした学会である。その模様をレポートする。
 大会長講演
大会長講演
大会長講演では,和歌山県立医科大学薬学部の岡田浩教授が登壇し,薬局の現状と将来像について語った。
世界で広がる「薬剤師が処方できる」流れ岡田教授は「薬局を取り巻く状況は大きく変わってきた」と切り出し,その背景として世界的な動きを紹介した。世界保健機関(WHO)と国際薬学連合(FIP)が2000年に「薬剤師は薬を渡すだけでなく患者ケアを提供すべき」と提言してから25年,薬剤師の業務は調剤にとどまらず,検査や予防接種,さらには処方まで担うようになりつつある。
例えば英国では,2026年以降の新卒の薬剤師は独立して処方できるようになる(一部の薬剤を除く)。既卒の薬剤師も,研修を修了すれば処方が可能となるという。その他にも,カナダ・アルバータ州では,一定の経験を積めば薬剤師が自らの判断で処方できる制度がすでに導入されている。
このような世界の流れを踏まえ,岡田教授は「高齢化と専門医偏在の進行により,地域で医師を維持することが難しくなっているなかで,薬剤師が地域医療を支える担い手となっている」と指摘した。
エビデンスが切り開く薬局の未来薬局での関わり方を工夫することで,患者の生活習慣の見直しや数値の改善につながることがある。岡田教授は,薬局での工夫ある声かけが患者の生活習慣の見直しにつながり,血糖や血圧の改善に結びついた事例を紹介した。「薬局は薬を渡す場所ではなく,人の行動の後押しする力をもつ場所だ」と強調する一方で,こうした取り組みの成果を社会に理解してもらうには,症例を並べるだけでは不十分であり,数値として示すことが欠かせないと語った。
実際に岡田教授が取り組んだ研究では,薬剤師の介入効果がデータで裏づけられている。カナダで行われた高血圧患者に対する薬剤師の介入研究を日本の人口にあてはめた試算では,薬局での継続的な取り組みにより,25年間で最大約20兆円の医療費削減につながる可能性を示している。
エビデンスは薬局の価値を社会に示すだけでなく,薬剤師自身の誇りややりがいにもつながる。現場の実践をデータとして積み重ねることが,職能拡大の意義を社会に伝え,その影響の大きさを裏づけるのである。
社会薬学が示すこれからの薬局像薬局は「薬を渡す場」から,人々の生活に寄り添い健康行動を支える拠点へと変わろうとしている。岡田教授の大会長講演は,その変化を世界の潮流と国内の課題の双方から示し,薬剤師が地域医療にどう関わるべきかを描き出した。社会薬学は,現場の実践とエビデンスを結びつけ,薬局の価値を社会に位置づける使命を担っている。
 特別講演
特別講演
特別講演では,京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野の中山健夫教授が,「科学的根拠に基づく医療(EBM)」と患者・医療者が治療方針をともに決める「Shared Decision Making(SDM)」をテーマに講演した。中山教授は,エビデンスやガイドラインが臨床現場で大きな道しるべになる一方で,「それがそのまま最適な答えになるわけではない」と指摘し,不確実性への向き合い方を論じた。
エビデンスとガイドラインの限界EBMの概念が提唱されてから30年以上が経ち,診療ガイドラインは科学的根拠を整理し,治療の推奨を示す文書として整備されてきた。しかし,中山教授は「ガイドラインに従えば必ずしも個々の患者に最適な結果が得られるわけではない」と述べる。エビデンスは臨床試験や観察研究から得られる科学的根拠である一方で,母集団からの推定がそのまま目の前の患者にあてはまるとは限らず,常に限界と不確実性を抱えている。
不確実性に向き合うEBM中山教授は,エビデンスは確実な答えを与えるものではなく,常に不確実性を含むと説明した。その不確実性にどう向き合うかこそが,EBMの本質だと強調する。EBMは,最良の科学的根拠に臨床経験と患者の価値観を加え,三者を統合して臨床判断を行うものと定義される。さらに教授は,このEBMを現場で具体化する方法の一つとして,SDMを位置づけた。
SDMとは何かSDMは,医療者と患者が選択肢のベネフィットとリスク,そして不確実性を共有し,患者の価値観や生活背景を踏まえて治療方針をともに考え,決めていくプロセスである。インフォームド・コンセントが「説明と同意」であるのに対し,SDMは「ともに考える医療」のかたちといえる。中山教授は,SDMは患者に一方的に決定を委ねるものではなく,医療者が情報を整理して提示し,患者が自分の価値観を伝えることで成り立つプロセスだと説明した。
また,中山教授は,数値や推奨だけでは患者が納得できない場面もあると指摘し,病気の受け止め方や生活の物語(ナラティブ)を理解することの重要性を強調した。
地域薬局に広がる視点中山教授は,エビデンスやガイドラインは治療方針を考えるうえでの重要な指針であるが,絶対的な答えにはならないと指摘する。だからこそ,不確実性のなかで患者の価値観や現場の状況と照らし合わせ,納得のいく選択を支えることがEBMの本質となる。その実践の一つがSDMである。こうした考え方は薬局での患者対応にも活かされ,薬剤師の役割を広げていく視点となる。
 シンポジウム3「拡大する薬剤師の役割:臨床研究と薬学教育」
シンポジウム3「拡大する薬剤師の役割:臨床研究と薬学教育」
シンポジウム3では,海外から2名の研究者が登壇し,薬剤師の職能拡大と患者利益への貢献について報告した。カナダ・アルバータ大学のRoss Tsuyuki教授と,オーストラリア・シドニー大学のCarl Schneider教授である。
カナダ・アルバータ州の挑戦Tsuyuki教授は,薬剤師が高血圧管理に主体的に関わった場合の効果を検証した臨床研究(RxACTION trial)を紹介した。アルバータ州では薬剤師に独立処方権が認められており,薬剤師がガイドラインに沿って降圧薬を開始・調整した結果,通常診療よりも血圧低下が大きく,収縮期血圧で有意な改善が確認された。さらに経済評価でも,この取り組みを広く実施すれば長期的に大きな医療費削減につながる可能性が示され,薬剤師の介入が社会的意義をもつことが裏づけられた。
この講演では続けて,Tsuyuki教授の研究室に所属するShanna Liu氏が,心血管リスク全体を視野に入れた包括的介入(PROACT study)を説明。血圧に加えて血糖・脂質・生活習慣を一体で評価し,ケースファインディング(潜在的患者の発見)から処方・生活支援・フォローアップまでを薬剤師が担うアルゴリズムを示した。薬局による継続的な関与が,高血圧にとどまらず慢性疾患全般に広がり得ることを示す取り組みである。
教育と評価が支える専門性Schneider教授は,薬剤師の活動を社会に理解してもらうには,その効果を患者の視点で評価することが重要だと述べた。単に薬を渡すのではなく,薬剤師の関与が患者の健康にどう役立ったかを示す必要があるという。そのために用いられるのが,PROMs(患者報告アウトカム指標)とPREMs(患者報告体験指標)である。前者は症状や生活の質の改善を患者自身がどう実感しているかを,後者は薬局サービスをどのように体験したかを測るものだ。Schneider教授は,日本の研究者とも共同で,薬局サービスを患者目線で評価するツールを開発していると紹介し,「薬剤師は安全で効果的な薬物療法に直結する存在だ」と語った。
日本の薬剤師への問いかけカナダやオーストラリアの事例は,薬剤師が慢性疾患管理に踏み込み,その成果をデータや患者の声で示すことで,社会的役割を拡大している姿を映し出していた。こうした流れを前に,日本の薬剤師も患者利益をいかに実現し,その価値をどう示していくのかを考える段階にある。今回の講演は,日本の薬局がこれから進むべき方向を見直すきっかけとなった。