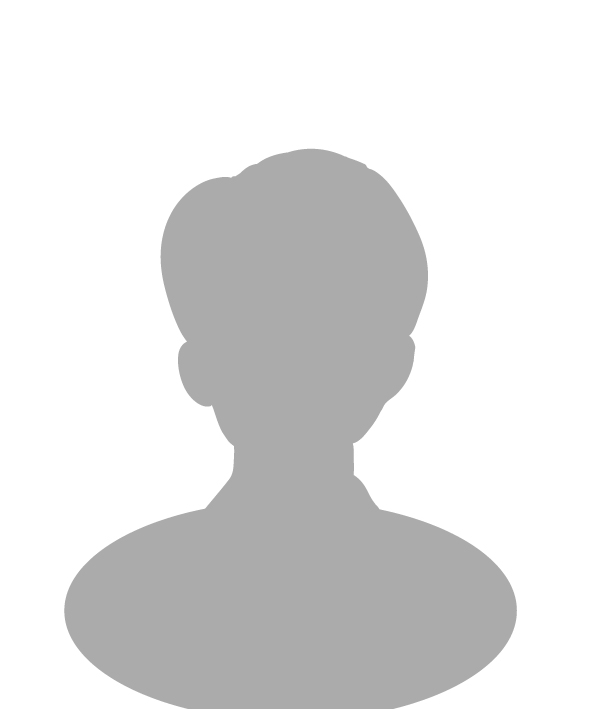【Interview】調剤と情報2025年7月増刊号『新・薬物アレルギーの教科書』の企画・編集者に聞く
【Interview】調剤と情報2025年7月増刊号『新・薬物アレルギーの教科書』の企画・編集者に聞く
薬物アレルギーに迷わないための視点
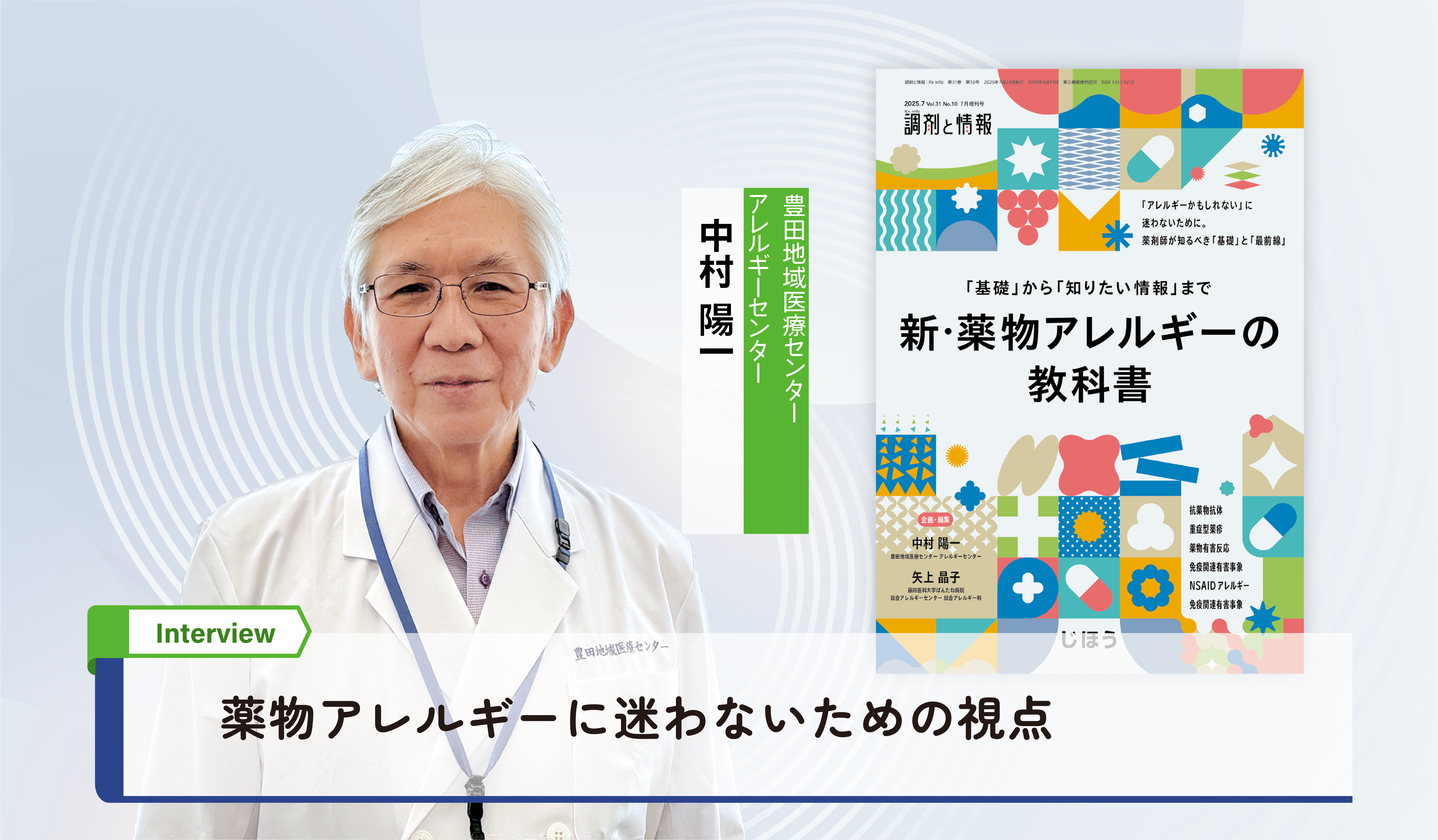
「薬を飲んでから,身体がちょっと痒い気がする」と患者から告げられたとき,薬剤師はただちに薬物アレルギーを疑うべきか,それとも他の可能性も視野に入れて慎重に判断すべきか,対応に迷う場面は少なくない。
薬物アレルギーの発症頻度は決して高くないが,見逃せば命に関わる事態に至ることもあり,適切な初期対応が求められる。一方で,「薬物アレルギーの既往」がある患者に対して,必要以上に薬剤を制限すれば,本来使用可能である薬まで遠ざけてしまう危険性もある。
そこで,本誌 2025 年 7 月増刊号『新・薬物アレルギーの教科書』の企画・編集を担当していただいた中村陽一氏(豊田地域医療センター)に,薬剤師が押さえておくべき基本的な視点と,実務における対応のヒントをうかがった。
──薬物アレルギーの発生頻度や,軽症~重症までの重篤度の分布など,疫学的な現状について教えてください。
薬物アレルギーの頻度は薬剤ごとに異なり,しかも確定診断が非常に難しいため,実際の発症率は「不明」とされることが多いのが現状です。ただし,そのなかでも発症しやすい薬剤はある程度明らかになっており,代表的なものとしては抗菌薬や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が挙げられます。なお,アナフィラキシーのデータになりますが発生頻度は,抗菌薬で約0.7%,NSAIDsで約0.1%と報告されており,薬物過敏症を含む軽症例を含めると,これらの薬剤では1〜数%程度になるのではないかと予想されます。
また疫学的にみると,薬物を原因とするアナフィラキシーによる死亡者数は,2015年以降,減少傾向を示していますが,その一方で,「原因不明」とされるアナフィラキシーによる死亡者数は増加しています。この理由の一つとして,相当数の薬物アレルギーが「原因不明」に含まれているのではないかと疑われています。特に近年は,生物学的製剤をはじめとした新しい薬剤の普及により,従来と異なるメカニズムによるアレルギー反応が生じている可能性があることも,その背景の一つとなっています。
──薬物アレルギーは,早期に適切な対応がなされれば重篤化を防げますが,発見が遅れると命に関わる事態へと進展することもあります。近年は,かかりつけ薬剤師制度や在宅医療の普及により,薬剤師が患者とより深く関わる場面が増えています。こうした現場において,薬剤師が薬物アレルギーに「気づく」ことには,どのような意義があるとお考えでしょうか。
薬物アレルギーが命に関わる事態とは,具体的にはアナフィラキシーを指します。この場合,可能な限り早期にアドレナリンを注射できるかどうかが,その後の転帰を左右する重要なポイントとなります。ここで注目すべきは,緊急時のアドレナリン自己注射が重篤な有害事象を引き起こす可能性は低く,「疑えば打つ」のほうが遙かにベネフィットが大きいという点です。したがって,可能な限り早期のアドレナリン注射を目指して,アナフィラキシーが疑われる場合,救急隊員の判断で,その場でアドレナリン自己注射薬を投与できるようにする実証実験的な取り組みも行われています。
また,薬物アレルギーは,いわゆる「2回目以降が危ない」という単純な話ではありません。交差反応などによってすでに感作されている場合は,初回投与でもアナフィラキシーを起こすことがありますし,これまで何度も内服していた薬で,ある日突然アナフィラキシーを発症することもあります。こうした不確実性を前提とすれば,薬剤師が「何かおかしい」と感じたときに薬物アレルギーの可能性を頭に置き,必要に応じて主治医や救急搬送へと橋渡しすることは,患者の安全を守るうえで極めて重要な役割だといえるでしょう。
──実際の現場では,薬物アレルギーに関する情報が乏しく,判断に迷う場面が少なくありません。例えば,薬物Aでアレルギー既往のある患者に対し,同系統の薬物Bが処方された際に,「化学構造が類似しているが,交差性はあるのか」「添付文書には何も書かれていないが,どう考えるべきか」と悩むことがあります。こうした現状を踏まえ,なぜ薬物アレルギーに関する情報はこれほど限られているのでしょうか。
そもそも薬物アレルギーの情報が蓄積・共有されにくい理由として,大きく三つの構造的要因が挙げられます。
一つ目は,確定診断の困難さです。薬物アレルギーは再投与による再現性の確認が基本とされますが,実際には重篤な事例では再投与ができないため,臨床現場では「疑い」のまま判断を保留せざるを得ないケースがほとんどです。このような確証のない事例は,副作用データベースや添付文書に反映されにくい傾向があります。
二つ目は,検査手法の限界です。皮膚テストや血液検査には対応可能な薬剤が限られ,また感度・特異度の問題から診断補助としての有効性にも限界があります。IgE介在性かどうかの区別すら困難なケースもあり,網羅的なデータ収集が進みにくいという事情があります。
三つ目は,交差反応性の予測困難性です。構造類似性があっても反応性が異なることがあり,薬剤代謝物の関与など,表面的な構造では判断できない場合も少なくありません。特にNSAIDsのように,不耐症やCOX選択性による差異が交錯する薬剤群では,反応の仕組み自体が複雑で,添付文書に一律に記載できる情報として整理することが難しいのです。
こうした背景のもと,薬物アレルギーに関する情報は個別の症例報告や限られた文献に散在しており,添付文書や公的データベースの記載に反映されにくい状況が続いています。そのため現場の薬剤師には,構造的類似性・交差性に対する理解や,個々の症例に即した慎重な判断が求められるのが実情です。
──今回,「新・薬物アレルギーの教科書」と題した増刊号では,薬物アレルギーに関する情報を,実務に役立つかたちで体系的にまとめていただきました。本誌を通して伝えたいポイントや,読者の薬剤師がどのように活用すべきかについて,お聞かせください。
本増刊号は,薬物アレルギー・薬物過敏症への対応について,薬剤師が実際の業務で判断に迷いやすい場面を意識して構成しています。従来型の網羅的な教科書とは異なり,実務上の悩みに対して「どう考えるか」「どのように整理するか」の手がかりを示せるよう意図しました。
薬物アレルギーは,明確な正解が得られないことも多く,情報が乏しいなかで意思決定を求められる領域です。そのため本誌では,不確実な状況でも判断の助けとなるような視点や注意点を,薬剤別にできる限り具体的に整理するよう努めました。
薬剤師の皆さんには,最初から通して読むというよりも,実務で疑問に直面したときに目次や索引から該当箇所を探して活用していただければと思います。迷ったときにすぐ開ける一冊として,現場で役立ててもらえたらうれしく思います。
──薬剤師には,薬物アレルギーを未然に防ぐだけでなく,過剰なアレルギー対策によって本来必要な治療を妨げることのないよう,適切な判断が求められます。アレルギー診療の専門家として,薬剤師に向けたメッセージをお願いいたします。
「アレルギーかもしれない」という段階で過度に反応してしまうと,実際には問題のない薬剤まで使えなくなり,結果として患者の治療の幅を狭めてしまうことがあります。特に小児の場合,一度「アレルギー」と記録されてしまうと,その先の医療でもずっとその前提で扱われてしまいがちです。一方で,重篤なアレルギー反応を見逃すことは,命に関わるリスクをはらんでいます。
薬剤師には,必要以上に恐れすぎることも,軽く見過ぎることもせず,根拠をもって適切に評価し,患者や医療チームに薬剤からみた「薬物アレルギー」の可能性を正しく伝え,ともに考える姿勢が求められます。そして,判断に迷う場面では,ためらわずに専門医につなぐことも,薬剤師の重要な責務の一つだと考えています。