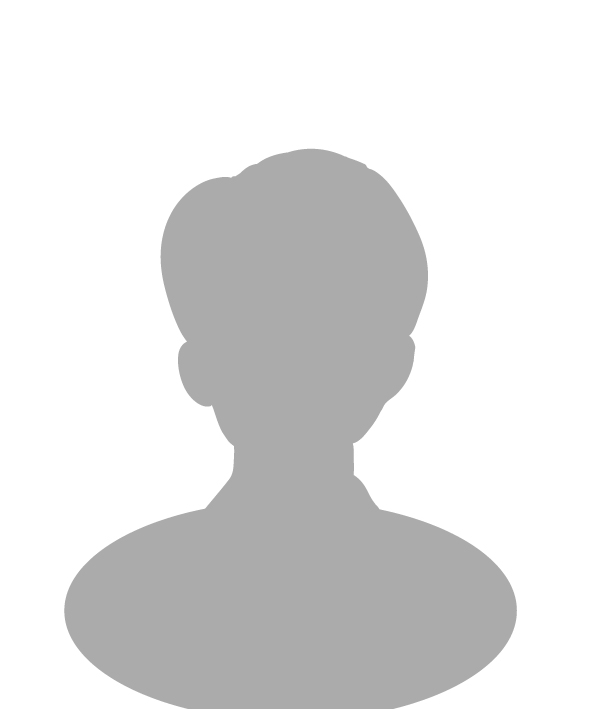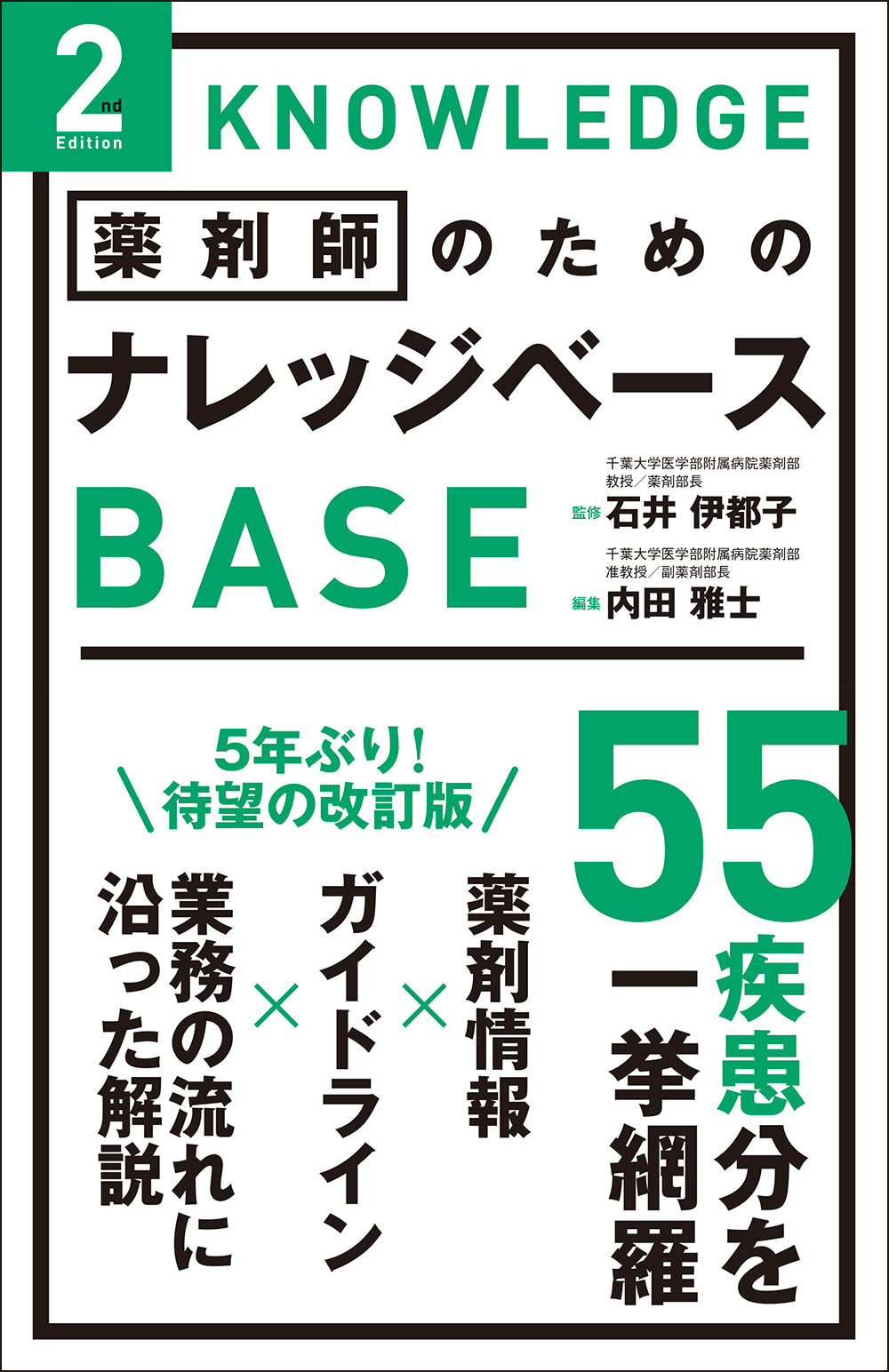【Interview】書籍『薬剤師のためのナレッジベース 2nd Edition』の監修者・編集者に聞く
【Interview】書籍『薬剤師のためのナレッジベース 2nd Edition』の監修者・編集者に聞く
臨床での壁を超える力に
薬剤師の進化を支えるナレッジベースの活用
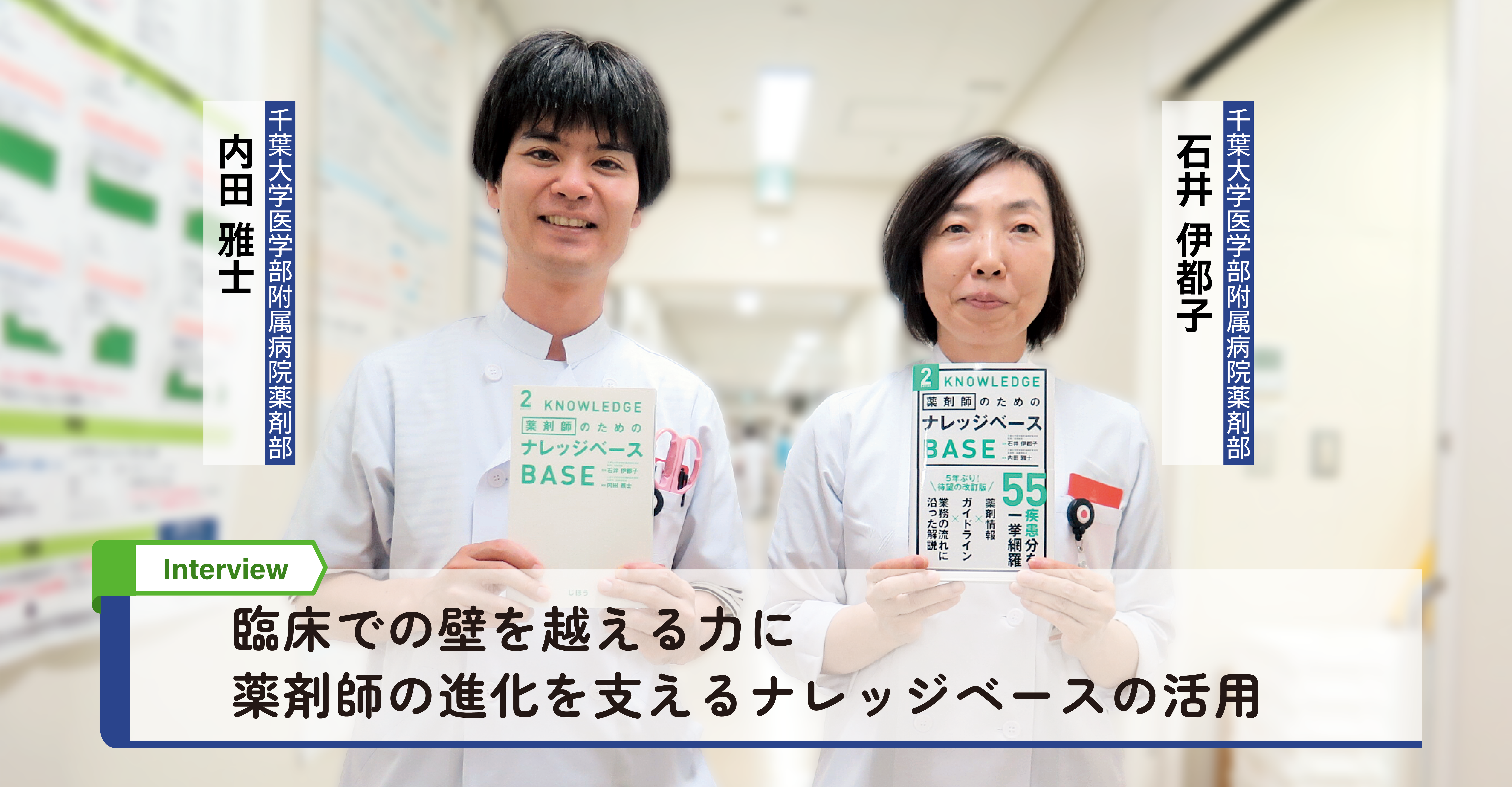
臨床現場で奮闘する薬剤師,特に新人・若手薬剤師にとって「羅針盤」のような存在となっている『薬剤師のためのナレッジベース』。2020年の初版刊行以来,多くの支持を集めてきた本書の第2版が刊行された。
監修者の千葉大学医学部附属病院・石井伊都子氏と編集者の内田雅士氏に,新人薬剤師が抱える課題と,これからの時代に求められる薬剤師像について想いを聞いた。
—— 新人薬剤師が現場で直面する「壁」とは?
(石井氏)入職したての新人薬剤師は,圧倒的に薬がわからないという状況にあります。それもそのはずで,病院には2,000種類以上の薬があるのです。また,国家試験を終えたばかりのときは,一般名は頭に入っていても,現場で使われる商品名となると途端にわからなくなりますし,薬剤の特徴についても抜け落ちてしまいがちです。毎年,新人が最初にそこで奮闘している光景をみてきました。

石井伊都子氏
(内田氏)新人薬剤師には,まず処方箋を見てその内容を監査してもらうのですが,どうしても時間がかかってしまいます。また,どこが重要なのかがよくわからないという声もよく聞きます。それから,病気の標準治療についての理解も大きな課題となっています。今は治療が個別化されていることもめずらしくありません。そのため,どこからが標準治療で,どこからが患者さん個別の治療なのか,その線引きが難しい点が新人薬剤師にとって困惑する要因となっているのでしょう。
(石井氏)薬剤師業務を難しくしている根本的な理由は,医師が診断している過程が目の前でみえないことです。診断の結果として出てきた処方箋が,突然,薬剤部にポンと飛んでくる。さらに,処方箋に複数の薬が処方されていれば,「これってどの病気に使うのだろう?」というところから推測しなくてはならないんです。この手探り状態から始めなければいけないというのが,薬剤師の仕事を身につけるうえでの一番の難しさであり,新人が最初に出くわす大きな壁なのだと思います。
—— 膨大な薬の情報とどう向き合えばよいのでしょうか?
(石井氏)最近の薬学教育には「知識の概念化」という考え方があります。これは,いろいろな経験を自分のなかで消化し,再構築していくイメージですね。最初は経験がなくてわからないことも多いと思いますが,調べながらでも前に進んで,まずは経験を蓄積していく。ただし,知識をただの記憶としてとどめるのではなく,作用機序やメカニズムといった基礎知識と結びつけて自分のなかで咀嚼することがとても大切です。そのうえで,自分の頭の使い方にあった方法で整理していくのです。やり方は人それぞれですが,ここは地道にコツコツ続けるしかないところだと思います。
(内田氏)難しい問いですが,薬剤師として働く以上,薬の知識は欠かせません。最近は「知識は外部に置いておき,必要な時にアクセスすればいい」という考えもありますが,知識と知識をつなげて応用するには,頭の中で情報をある程度整理しておく必要があります。ですから,基礎となる知識は最低限インプットしておくことが重要です。とはいえ,それだけでは不十分で,知識というのは患者さんから学ぶ部分も大きいと感じています。患者さんが抱えている薬学的な課題を見つけ,「わからない」と思って必死に調べる。そのプロセスを何度も繰り返すうちに,関連事項も調べるようになり,知識が補完されていきます。
(石井氏)そうした「調べる」という行為を助けるために,私たちはこの本を作りました。薬がわからないときには,まず調べるためのツールが必要ですよね。本書はガイドラインをベースに情報を整理しているので,体系的に頭に入りやすいと思います。もちろん,一度見ただけでは覚えきれませんから,何度も繰り返し使っていただきたい。同じ薬効なのに違う薬が処方されている理由など,疑問が湧いたときにでも,パッと開いてもらえれば短時間でヒントがみつかるはずです。
(内田氏)私はこの本を,コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスに優れた「旅行のガイドブック」だと思っています。ガイドブックって,行き先や観光地のポイントをサッと調べられるのがよいですよね。この本も同じで,学びたい疾患領域や薬物指導のポイントなど,わからないことがあったときに気軽に調べられるツールとして使ってもらえたら嬉しいです。

内田雅士氏
—— 薬剤師に求められる役割は今どう変わってきていますか?
(石井氏)最近では,薬剤師は「疑義照会をする人」や「安全性を守る人」から,「薬物治療全体をマネジメントする人」というイメージに変わってきていると感じています。背景には,医師の専門分化が進んでいることがあります。高齢化社会で複数の合併症をもつ患者さんが当たり前になると,薬物治療全体を俯瞰してみられる人が必要になり,その重要な役割を担うのが薬剤師です。
また,業務範囲も広がっています。以前は薬を渡す前の監査や服薬指導が中心でしたが,いまでは投与後のモニタリングまで求められるようになりました。薬を飲んでもらう前から飲んだ後まで,すべての過程をフォローするのが薬剤師の仕事になってきています。そのためには,病院と薬局の連携が不可欠です。最近では院外処方箋に検査値を表記したり,退院時に情報共有したりと,連携が進んできました。病院薬剤師も薬局薬剤師も共通の土台に立つことがより重要となっています。
—— この本を,読者にどのように活用してほしいですか?
(石井氏)本書は「治療薬チェックリスト」,「ガイドラインに基づく基本情報」,「薬物治療の詳細」という3段階の構成になっています。これは薬剤師の業務の流れを意識したものです。チェックリストと詳細解説を行ったり来たりしながら使うことで,「知識の概念化」を頭の中で実践していけると思います。
毎日の業務では,どんなにキャリアがあっても必ずわからないことや壁にぶつかります。そういったときに,この本が仕事のスムーズな進行を助け,患者さんにとって有益な提案につながれば,これほど嬉しいことはありません。
(内田氏)本書はさまざまな疾患の治療のエッセンスを整理したものです。まずはこの本を実務で使っていただいて,日々の疑問を手軽に解決するツールとして活用してください。そして,この本をきっかけにして,より深くて広い薬物治療の勉強や理解へとつなげていってほしいと願っていま す。