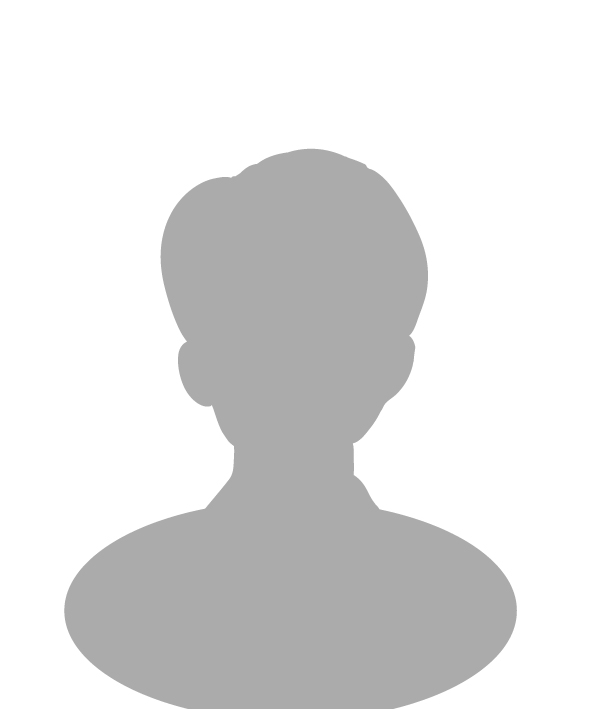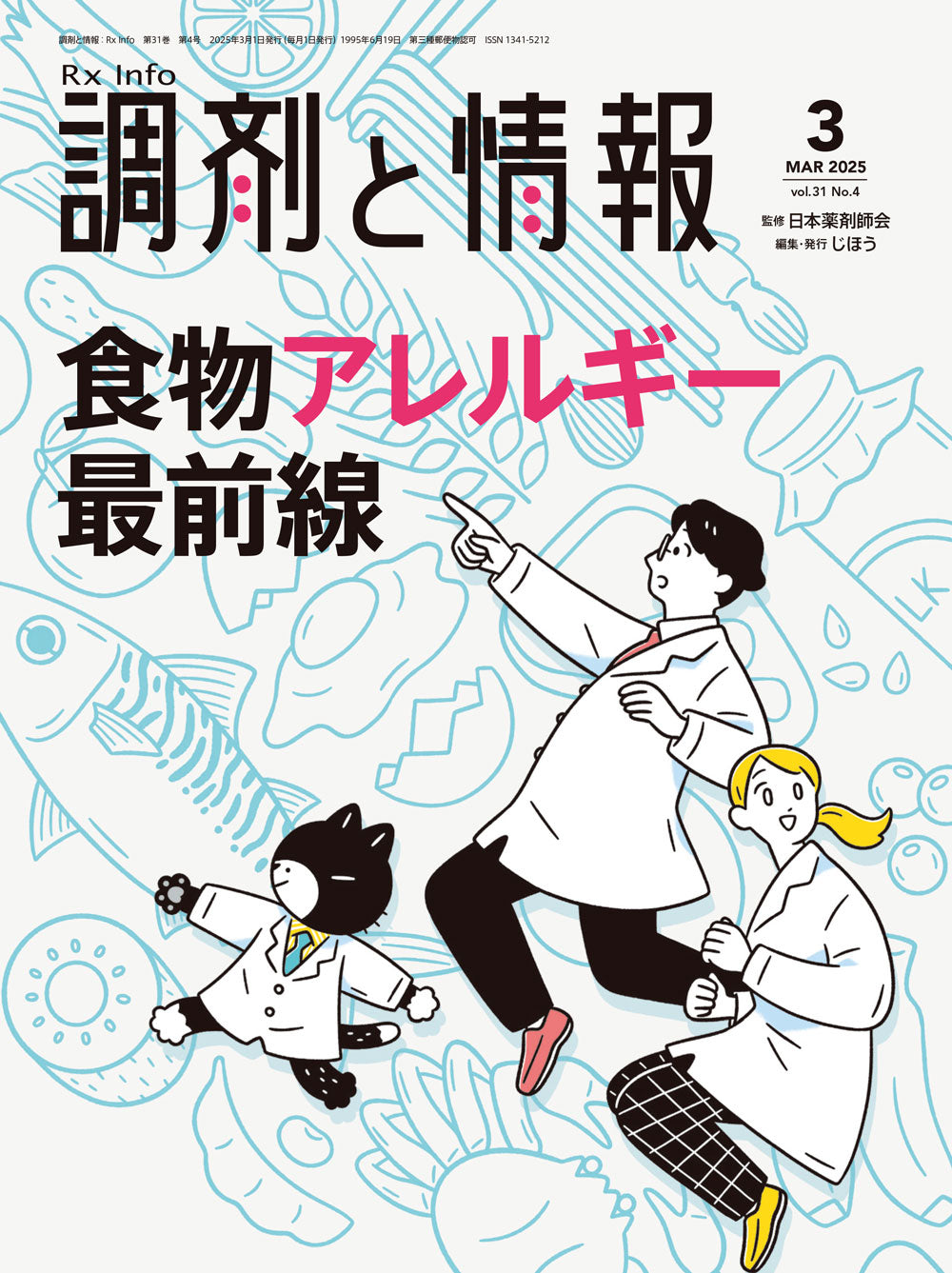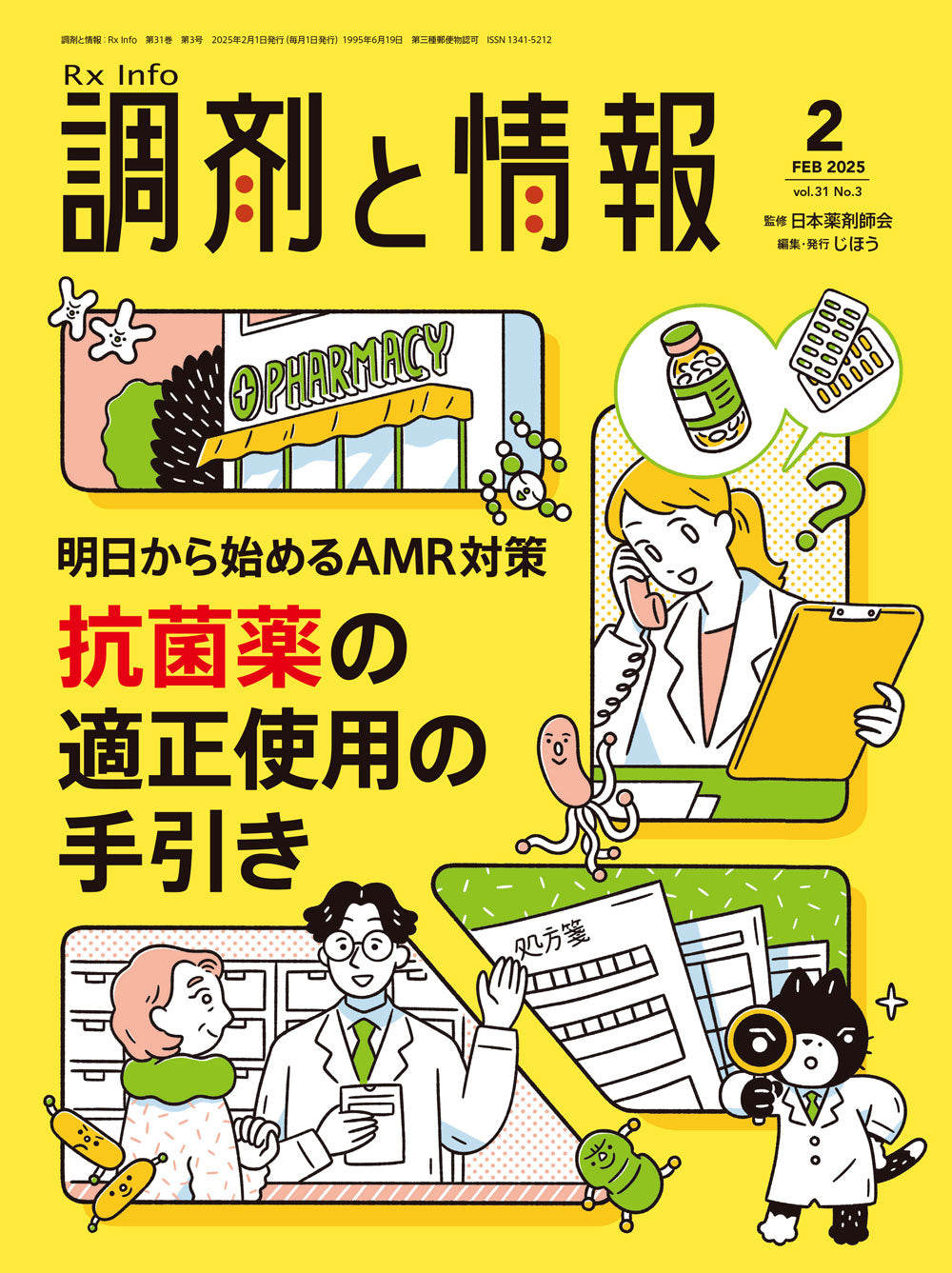【Interview】アレルギーの専門家に聞く
【Interview】アレルギーの専門家に聞く
「ヒスタミン中毒」より圧倒的に多い「アニサキスアレルギー」について

—— 魚介類のアレルギー様症状において「ヒスタミン中毒」よりも「アニサキスアレルギー」のほうが圧倒的に多いとのことですが,詳しく教えていただけますでしょうか?
(中村)アニサキスは,サバ,アジ,イカなどの内臓に寄生している,体長 2~ 3cmほどの寄生虫の一種で,生きたアニサキスを摂取することで発症する「胃(腸)アニサキス症」が有名です。また,アニサキスのタンパク質がアレルゲンとして抗原性を示し,蕁麻疹などの症状を伴う「アニサキスアレルギー」を引き起こすことがあります。
ちなみに,「魚を食べると蕁麻疹がでる」と訴える人のうち,実は魚アレルギーの人は少なく,成人の場合は,そのほとんどがアニサキスアレルギーです。なお,子どもの場合は,アニサキスに感作されていないことが多いため,魚アレルギーを最初に疑って よいと思います。
一方でヒスタミン中毒は,魚などに含まれるヒスチジンからヒスタミンが多量に生成されることにより生じるアレルギー様症状です。ヒスタミンの生成は細菌によるものであり,それ相応の時間と細菌が活動できる環境など,いくつかの条件を満たす必要があります。そのため,特に一般家庭では,ヒスタミン生成の条件を満たす場面は少なく,ヒスタミン中毒になる人は少ないのです。
魚を食べた後に起こるアレルギー様症状として,アニサキスアレルギーもヒスタミン中毒も似ている部分がありますが,臨床ではアニサキスアレルギーのほうが多いと感じるのは確かです。なお,ヒスタミン中毒における代表的な魚といえばマグロなどの赤身魚ですが,アニサキスアレルギーも赤身魚に多いと言われているので,魚種だけでの鑑別は困難です。また,アレルギー専門医でない医師の場合,アニサキスアレルギーを知らずに,いわゆる “ゴミ箱的な診断 ”でヒスタミン中毒と決めつけてしまう場合も少なくありません。したがって,誤ってヒスタミン中毒と診断されていることも考えられ,アニサキスアレルギーをもつ人の数は実際にはかなり多いと思います。
—— アニサキスは赤身魚と関連することが多いとのことですが,アニサキスアレルギーが疑われる場合,どのような魚に注意したらよいでしょうか?
(中村)教科書的にはサバ,アジ,イカなどが挙げられますが,これら以外の魚から検出されたとの報告も多く,わからないことも多々残されているというのが現状です。また,アニサキスがいないとされる魚だとしても,まな板の上に他の魚由来のアニサキスやアニサキスタンパク質が存在する可能性を否定できません。そのため,特に外食などで魚を食べる場合は注意が必要といえます。
—— アニサキスによる食中毒として有名なのは,やはり「胃(腸)アニサキス症」ですが,「アニサキスアレルギー」との違いについて教えていただけますでしょうか?
(中村)
以前は,胃アニサキス症とアニサキスアレルギーは,まったく別のものと考えられていましたが,胃アニサキス症の患者に対してアニサキスのアレルギー検査を行うと,陽性となるケースが多く,近年は両者の関連性が指摘されています。また,胃アニサキス症では急激な胃痛を伴いますが,抗アレルギー薬を注射すると,痛みが速やかに軽減したという報告があり,胃痛はアレルギー反応によるものである可能性もあります。また,健診などで胃内視鏡をすると,“無症状 ”なのに胃にアニサキスがみつかる人がいるのですが,アニサキスに対するアレルギー反応がないため無症状であると説明することができるのです。
ただし,胃アニサキス症とアニサキスアレルギーが同じものであるということでは,もちろんありません。胃アニサキス症の場合は,生きたアニサキスを摂取して起こりますが,アニサキスアレルギーの場合は,アニサキスの生死に関係なくアレルギー反応が起こります。つまり,アニサキスアレルギーという広い枠組みのなかに,胃アニサキス症が含まれているというイメージです。ただし,例外的なケースもあるため,さらなる調査研究が必要です。
—— 「胃(腸)アニサキス症」の場合,よく焼く,よく噛む,内臓周辺は食べないようにするなどの対策が考えられますが「アニサキスアレルギー」の場合,対策などはあるのでしょうか?
(中村)
基本的には寄生率が高い魚介類は,完全除去すべきだと思います。寄生率が低い魚についても症状誘発の可能性は残りますが,せめて加熱調理をして摂取したほうが安全です。アニサキス抗原は熱に強いことが知られていますが,それでも熱処理によるリスク低減は期待できることから,加熱調理が対策の一つだと思います。実際,アニサキスアレルギーを発症した人のほとんどは,生魚を食べたことで発症していると思います。
—— 加熱調理という視点でいうと,果物の抗原性はかなり熱により減弱するそうですね。例えば,生のリンゴではアレルギー症状が起こるけど,アップルパイであれば起こらないというようなことがあるということでしょうか?
(中村)そうですね。アップルパイでリンゴアレルギーを生じる人はほとんどいないと思います。また,大豆アレルギーも同様で,大豆アレルギーをもっている人でも,醤油や味噌,豆腐などは大丈夫という人がほとんどです。ただし,豆乳は大豆の抗原を濃縮したようなものなので,リスクが高いです。
—— 他にも,果物と花粉症の関係や,食用昆虫とエビカニアレルギーの交差抗原性など,教えていただきたいことがたくさんあるのですが,来月号(本誌2025年 3月号)では「食物アレルギー最前線」と題して中村先生に特集をオーガナイズしていただきました。最後に,来月号がどのような内容なのか教えていただけますか?
(中村)アレルギー領域で日本を代表する方々に執筆いただいているので,文字通り食物アレルギーの “最前線 ”を表す特集になると思います。また,食物アレルギーというと,これまで小児科領域で注目されてきましたが,近年は成人ではじめて発症する食物アレルギーも増えており,新しい知見を得られる機会になると思います。その他にも「花粉‒食物アレルギー症候群」「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」など,興味深いテーマが多く並んでいますので,来月号を楽しみにしていただければと思います。