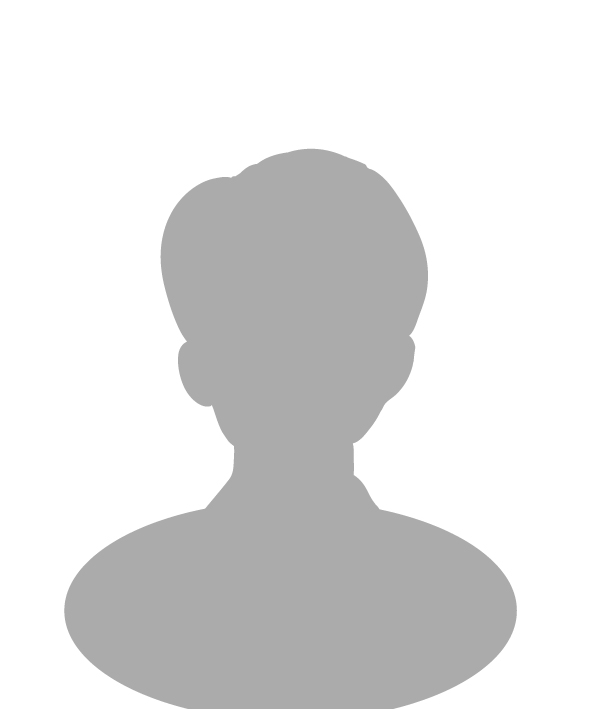第18回 日本薬局学会学術総会
第18回 日本薬局学会学術総会
在宅緩和ケアにおけるさらなる活躍に期待
シンポジウム2「住み慣れた地域での生活を最後のその時まで支えるために ~在宅緩和ケアにおける多職種連携で薬剤師が果たすべき役割~」では,佐々木淳氏(医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長)が「在宅緩和ケア医が薬局薬剤師に望むこと」と題し講演を行った。そのなかで,在宅を望む患者が退院できずに最期を迎えてしまう現状に触れ,「改善のためには休日や夜間の在宅緩和ケア体制の充実が必要」であるとして,薬局薬剤師のさらなる積極的な介入を呼びかけた。
佐々木氏は終末期がん患者の7割が「自宅で最期を迎えたい」とする一方で,8割以上のがん患者が退院できずに亡くなっていることを紹介。その要因として,① 意思決定支援が十分にできていないこと,② 末期がん患者の身体状況は加速度的に悪化し,退院支援のための十分な時間が確保できないこと,③地域の在宅緩和ケアを行える体制が整っていないこと——の3つを挙げた。
がんと診断されてからはさまざまな検査,治療の介入があり,終末期では症状も急激に悪化していくため,患者を取り巻く状況は目まぐるしく変化していく。そのような状況下では,患者が現状を受け入れ,意思決定をする余裕がないという,がん治療における構造的問題を指摘した。また,がん治療においては短期間にさまざまな専門医がバトンタッチしながら検査,治療を進めていくため,患者にとって,かかりつけ医とよべる存在がいないことも問題であるとした。一方で,診断前から患者と接し続けている薬剤師は,身体状況が悪化してしまう前から退院支援を行うことのできる数少ない「かかりつけ機能」を発揮できる存在だと語った。
また,地域の在宅緩和ケアの体制については,医療従事者による改善の余地が最も大きいとして,さらなる在宅緩和ケアのサポート体制充実を求めた。在宅緩和ケアでは,患者宅まで医薬品を届けるが,休日や夜間も,そうした対応ができる薬局・薬剤師は,都市部でもまだまだ少ないのが現状である。佐々木氏の調査によると,休日対応や24時間対応を標榜する首都圏の薬局のうち,実際には65%程度しか調剤の対応ができておらず,患者が安心して在宅緩和ケアを受けられないケースも少なくないという。そのため,24時間対応で「調剤」と「適切な情報提供」を行える薬局・薬剤師が,在宅緩和ケアを推し進めるために必須であるとし,薬剤師のさらなる職能の発揮に期待を寄せた。