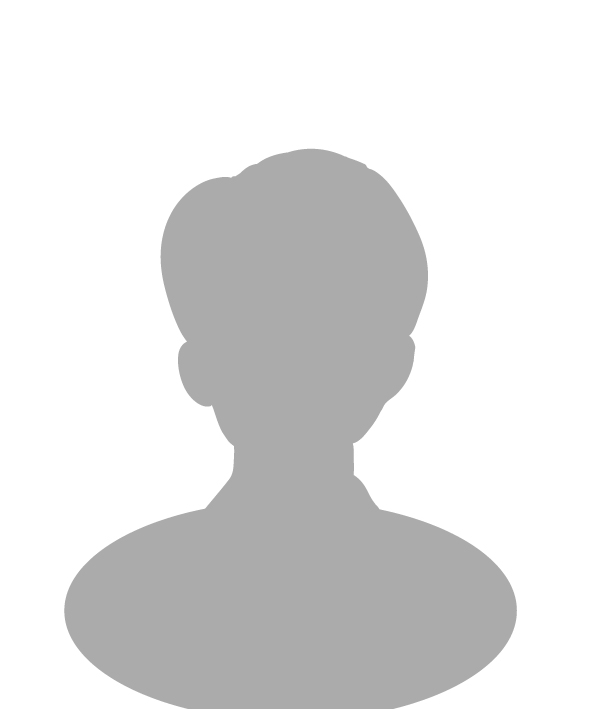獣医療における薬物治療の現状と課題
獣医療における薬物治療の現状と課題
——犬や猫といった伴侶動物,また馬や牛などの家畜,さらにはイルカやクジラなど,獣医療ではさまざまな動物に対して治療を行いますが,ヒトに対する薬物治療とどのような違いがあるのでしょうか。
折戸 ご質問のとおり,一番大きな違いは対象となる動物種があまりにも多様であることです。動物種が違えば,薬物代謝酵素の発現量や種類も違います。また,同じ犬であってもチワワとイングリシュ・マスティフでは,体重が100倍近く違う場合もあり,このような症例はヒト医療ではまず考えられないと思います。
薬物治療に注目してみると,農林水産省が承認している動物用医薬品もありますが,実際にはそれだけでは選択肢が足りません。そこでヒト用の医薬品を転用することも多いのです。ただ,ヒト医療のように十分なエビデンスがあるものだけではありません。そのため,ヒトでの使用経験をもとに,体重換算や体表面積換算で適切な投与量を推測して使っているというのが現状です。
さらに興味深いのは,動物は言葉での指示を理解してくれないという点も挙げられます。例えばアトピー性皮膚炎の場合,ヒトなら「掻くと悪化しますよ」と説明すれば理解してもらえますが,動物にはそれが通じない。だから,ヒトなら軽い痒み止めで済むケースでも,動物では最初から強い薬でしっかり痒みを止めたほうが良い結果につながることもあります。こういった,ヒト医療とはまったく違う発想が必要というのも獣医療の特徴かもしれません。

——実際のところ,例えば犬と猫では薬物に対し,どのような薬物動態学的な違いがあるのでしょうか。
折戸 吸収・分布・代謝・排泄のなかで,動物種によって最も差が大きいのは代謝だと思います。例えば,バルプロ酸の消失半減期は犬だと1~3時間程度と非常に短いのに対し,ヒト(成人)では9~16時間と大きな違いがあります。このような代謝速度の差は,投与間隔や用量設定,さらには有効性に大きく影響します。
犬種による違いも重要です。例えば,コリー系の犬種の一部では,遺伝的にP糖タンパク質の機能が著しく低い群がいます。P糖タンパク質は薬物動態に関与する重要なトランスポーターですから,コリー系に対し薬物治療を行う際は,そのことも踏まえて投与量を検討する必要があります。
猫については,グルクロン酸抱合能が低いという特徴があります。アセトアミノフェンなど,この経路で代謝される薬物は猫では致命的になる可能性があるため,使用は避けるべきです。
——ヒト医療の世界において,少し前に「薬も出してくれない」と文句を言う患者がいると話題になったことがあります。獣医療は原則自由診療であるため,薬剤費が掛からなければ治療代が安くなり喜ばれそうな一方,せっかくお金と時間をかけて来院したのに「薬も出してくれないのか」と不満を言う飼い主さんもいそうな気がしますが,実際はどうなのでしょうか。
伊藤 そういう飼い主さんも確かにいらっしゃいます。ただ,われわれ獣医師も「薬は必要ない」と根拠をもって診断しているので,どうして薬が必要ないのかを丁寧に説明していく必要があります。一方で,獣医療の世界では「痒がっているので診てほしい」と言われたときに,その痒みの原因を追究すべきなのか,かゆみ止めの薬を出して様子見にしておくのか,判断がとても難しいところがあります。例えば,猫の口内炎を考えてみましょう。口内炎の治療法の一つに歯を抜くというものがあり,猫のことを考えると,それがよい場合があるのですが,全身麻酔をかけて手術することになるため,ステロイドで対症療法をするよりも技術的なハードルが上がりますし,飼い主さんの心理的負担や経済的負担も大きくなります。
したがって,動物の状態,病気の進行度をひっくるめて,飼い主さんがどこまでの治療を求めているのか,保険診療ではないので飼い主さんの経済状況はどうなのかなど,さまざまな背景を踏まえて個別に判断を求められるのが獣医療でもあります。
——獣医療の世界においても,基礎研究や臨床研究が行われているかと思います。しかしながら,犬だけでも500種類以上いるともいわれ,雑種も含めればその数はさらに多いのではないかと考えられます。このような背景のなか,薬物治療に関する情報はどのように扱われているのでしょうか。
折戸 獣医療の世界には,コンセンサスステートメントという,ヒト医療でいうガイドラインに相当するものがあります。これは専門医が多数の論文を精査し,エビデンスレベルの高い治療法を整理したものです。最近は,こうしたエビデンスに基づいた治療が増えてきています。
実臨床では,犬種ごとの細かい違いよりも「犬」「猫」という大きな括りで考えることが多いです。もちろん,秋田犬や柴犬のタマネギ中毒のような犬種特有の注意点は把握していますが,基本的には種レベルでの文献を参考にしています。
また,ヒト用医薬品の動物実験データも貴重な情報源になっています。ヒト用医薬品の開発過程では必ず動物実験が行われているので,そこで得られた毒性データや薬物動態のデータは,獣医療にも活用できます。こうした情報を総合的に判断しながら,それぞれの動物に最適な治療を選択していくのが現状です。
——薬を飲ませることに苦労されているという話をよく聞きますが,実際はどうでしょうか。
折戸 薬を動物に飲ませるというのは,本当に大変な作業です。子どもに薬を飲ませるのに苦労するという話はよくありますが,動物の場合は言葉での説明が通じないため,より困難です。ある製薬メーカーが獣医師を対象に行った慢性腎臓病治療薬に関するアンケートでは,「飲ませやすさ」が最も重要視される項目として挙げられました。「薬効」よりも「飲ませやすさ」が優先されるという事実は,現場での苦労を如実に表しています。
このように獣医療では,とにかく経口投与は苦労が多いのですが,言い換えれば違う投与経路が重宝されやすいともいえます。例えば,猫の食欲増進剤というものがあります。猫はとても神経質なので,カプセルのような剤形をエサに混ぜてもまず飲んでくれません。また,無理やり飲ませるのも飼い主さんの負担が大きいですし,そもそも食欲がない猫に内服させることは困難です。では猫の食欲増進剤の投与経路はどうするかというと,「耳に塗る」という剤形が採用されているものがあります。その他にも,犬の目から吸収させる催吐薬など,ヒト医療の世界では考えにくい方法をとっている場合もあります。
 獣医師から薬剤師への期待と不安
獣医師から薬剤師への期待と不安
——獣医学部でも医学部と同様に薬理の講義があると思いますが,医学部のように深い薬学的知識を学ぶわけではないと聞いたことがあります。実際のところはどうなのでしょうか。また,犬や猫などの種差について獣医療の現場ではどのように考えているのでしょうか。
伊藤 正直なところ,薬剤師さんの薬に関する知識に比べたら,獣医師の知識は比較にならないほど浅いと思います。ヒト用の医療医薬品の添付文書を読むことがあるのですが,薬剤師さんはこれをすべて理解できるのかと思うと,知識の深さには驚かされます。大学時代の薬理学の講義は,基本的には少なく,卒業後に現場で実践的に学んでいくのが実情です。私も,1年目や2年目のころは「犬の場合は……猫の場合は……」と,夜遅くまで勉強する毎日でした。
種差についてですが,確かに固有の違いがあり注意が必要な場合もあります。しかし基本的には,犬も猫もヒトも同じ哺乳類であり,大きな違いはそれほどないのではないかと思います。
——獣医師からみた薬剤師への期待や不安はありますか。
伊藤 前述のとおり,獣医師の薬に対する知識は明確に不足しています。過去勤務してきた動物病院も含めて,薬に関するインシデントは少なくなく,どこの動物病院も不安を抱えていると思います。したがって,薬剤師さんと協力関係を築ければ,より良い獣医療への期待は大きいと思います。
一方で,獣医療とヒト医療では「治療目標」という点で明確に違いがあります。ヒト医療の場合は,検査で異常がなければ「よかったね」となりますが,獣医療の場合は「何万円もかけて検査したのに何もわからないってどういうこと?」ということは常にあるのです。
薬物治療においても同様で,ヒト医療の場合は「この薬のほうが効果が出る可能性がある」ということであれば,それがファーストチョイスになるかと思いますが,獣医療の場合は,薬剤の金額はどうなのか,費用対効果はどの程度期待できるのかといった経済的な問題や,1日何回飲ませないといけないのかなどの飼い主さんの心理的負担,そして飼い主さんがどういった治療目標をもっているのかによって,薬剤の選択が変わることがあるということです。
ヒト医療ではベストがファーストチョイスでも,獣医療ではベストではない方法だけど,8割の質で費用が6割というのが飼い主さんにとってはベストチョイスになることがあるのです。こういった感覚はヒト医療にはないので,薬剤師さんがどのようにわれわれの現場を理解してくれるのか不安を感じる部分があります。

聴診をする伊藤太一氏
 獣医療における薬剤師の可能性
獣医療における薬剤師の可能性
——薬剤師は,ヒトのことしかわかりませんが,獣医療の世界で薬剤師の知識は求められているのでしょうか。
伊藤 薬剤師さんに何を相談すればよいかもわからないほど,薬の知識に乏しい獣医師がほとんどではないかと思います。
獣医療の多くはヒトからの外挿です。したがって,「ヒトではこういう使い方をする」「こちらの薬のほうが臨床成績が良い」「この薬とこの薬の組み合わせは,ヒトでは使わない」「処方内容に重複がある」など,ヒト医療で行われている処方提案や処方監査の視点で情報提供をいただければ,獣医師がそれを動物にあてはめられるのか検討すればよいだけですので,獣医師たちからの需要も高いのではないかと思います。
そういった意味で,獣医師と薬剤師が協力することで,より良い獣医療を実現できる可能性があると期待しています。
折戸 薬剤師さんは化学構造式から薬効や薬物相互作用など,われわれと違う視点で推測や予測することができたり,ヒトでのエビデンスを知っています。そうした薬学的な視点から「この組み合わせは相互作用のリスクがある」とか「ヒトではこちらの薬のほうが第一選択になっている」といった情報をいただけると,獣医療の質は確実に上がると思います。
ただ,獣医師と薬剤師では,薬に対する考え方や視点が違うので,お互いの立場を理解しながら,どこで協力できるか,どのように線引きをするか,といった部分を丁寧に詰めていく必要があるでしょう。詰めなくてはいけない課題はあるものの,大きな可能性を秘めている,そんな気持ちでいます。
 獣医療と薬剤師の連携のかたち
獣医療と薬剤師の連携のかたち
——薬局薬剤師が動物病院や獣医療に関われる連携はありますか。
櫻井 近年,動物病院での処方や調剤に関して,薬剤師がサポートできる場面は少しずつ増えてきていると感じています。例えば,薬剤師が剤形や安定性,投与間隔の工夫に関する情報を提供することで,獣医師の処方設計の幅は広がります。また飼い主に対しても,自宅で安全に投薬できるよう,薬の保管方法や投与のコツなどを,薬剤師の立場から助言することも有益な情報提供だと思います。
具体的には,ここまで何度も登場しているように,猫はアセトアミノフェンを誤飲すると重篤な中毒を起こしますが,猫を飼っている人の約半数が医薬品を出しっぱなしにしているという調査があります。アセトアミノフェンを含有するOTC医薬品も多いですから,服薬指導や薬の受け渡しの際に「ペットを飼っていますか?」と一言,声を掛けることも獣医療への関わり方の一つだと思います。病気の治療という視点だけでなく,薬の安全という視点でヒト医療と獣医療の両方を評価できるのは,薬剤師ならではの強みだと思います。
また,地域の健康イベントなどで,動物病院と協力して,ヒトとペットの両方の健康相談ができるというブースを出すことも一つのアイディアかもしれません。動物の薬の話も薬剤師に相談してよいんだという認識を飼い主と獣医師に広げていくことが大切です。
さらに,在宅医療の分野でも連携の可能性があります。高齢の方がペットを飼っていたり,ペット自身が高齢でなかなか病院に通えないというケースでは,獣医師が往診をするのですが,手持ちの医薬品や医薬品情報,調剤に困るということもありますので,薬局と連携するということも考えられるかもしれません。
近い未来,飼い主とペットの両方の健康を地域の医師,獣医師,薬剤師が連携しながら支えていくという社会が期待されます。
 獣医療における薬学研修プログラムを通した取り組み
獣医療における薬学研修プログラムを通した取り組み
——東京薬科大学では,『獣医療における薬学研修プログラム』を開始したそうですが,どういったプログラムなのでしょうか。
櫻井 2025年10月24日より「獣医療における薬学研修プログラム」の受講を開始しました。これは,獣医師,愛玩動物看護師,薬剤師が連携できる基盤を整えることを目的にしたプログラムで,薬剤師が獣医療に必要な知識を体系的に学ぶ機会を創出するというねらいがあります。
講義内容は,「獣医薬理学」「機能形態学」「愛護・適正飼養学・保定」「飼い主とのコミュニケーション・ペットロス」「獣医療関連法規・愛玩動物における倫理」「製剤学,投与方法,チーム獣医療,飼い主の犬・猫アレルギー」「薬剤管理・服薬指導」と網羅的で,獣医療の視点から薬学的理解を深められるように構成しています。なお,プログラムはオンデマンド形式で,全プログラムを修了した方には修了証を発行します。
薬局の業務をしながら,ペットも含めた地域の健康を支援する存在として,獣医学と薬学のコラボレーションによる新たな可能性を探る第一歩にしたいと思っています。
 "生命"を支える薬剤師へ
"生命"を支える薬剤師へ
——最後に薬剤師に向けたメッセージをお願いします。
櫻井 まず何よりもお伝えしたいのは,獣医療における連携の前提となる理念についてです。獣医師をはじめ,獣医療に関わる者は何よりも動物福祉(animal welfare)の観点から,その動物にとって最善の判断を行うことが求められます。動物福祉とは,動物たちの限られた命の時間のなかで,痛みや苦しみをできるだけ減らし,その動物がその動物らしく生きることを意味します。この動物福祉を支えること,それが獣医療に関わる者の使命です。
ヒト医療においても同様の理念を考えることはできますが,獣医療の場合は,動物が自ら症状を訴えることができません。そのため,治療や薬剤の選択には,科学的知識とともに,命への想像力がヒト医療以上に求められます。だからこそ獣医師の臨床経験に薬剤師の薬学的専門性が加わることで,動物にとっても飼い主にとっても,より良い医療が実現できると考えています。
もう一つ大切なこととして,獣医療とヒト医療では文化や考え方に違いがあることを理解し,獣医師も薬剤師も互いに,それぞれの専門性を尊重することが大切です。ヒト医療ではありえないような処方であっても,獣医療ではありえます。なぜ,それが「あり得るのか」を薬剤師が理解し,「なぜあり得ないのか」を獣医師と共有することが,一歩進んだ獣医療につながっているのかもしれません。
こうした相互理解の先に,私たちが見据えるべきは飼い主と動物たちです。飼い主が安心して,大事な家族である動物に治療を受けさせられることが最終目標です。「ヒトで効いたから猫にも大丈夫」という説明では飼い主さんは安心しません。動物それぞれの特性を理解し,適切に伝えることが求められます。すべての"生命"を支える薬剤師として,獣医師・薬剤師・飼い主・動物という関係性を常に意識していただきたいと思います。
このプログラムを通じて,それぞれの薬剤師が独自のアイデアを持って,どのようなかたちで獣医療に貢献できるか考えていただきたい。その可能性は無限大だと信じています。
 獣医師とのコラボレーションが産む
獣医師とのコラボレーションが産む