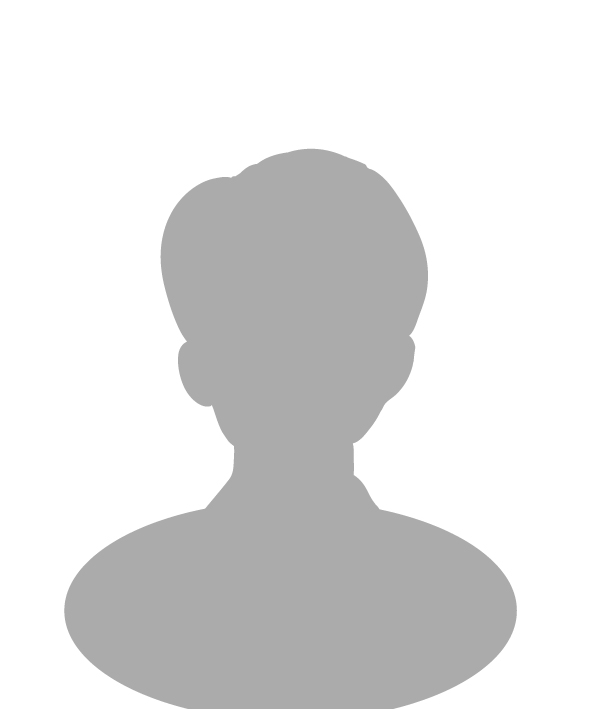アカモクうどんから広がる,
アカモクうどんから広がる,
"塩"をおいしく減らす新しい習慣

こうしたなかで注目されているのが,社会全体の食環境を変えていく「社会的減塩」の取り組みです。その中核をなすのが,消費者に気づかれないように少しずつ塩分を減らす“こっそり減塩”です。国内外で研究や実践が進み,食品メーカーや飲食業界でも応用が広がりつつあります。
「RxInfo TV」第15回では,「おいしい社会的減塩」に取り組まれている水田先生に,その意義や実際の工夫,薬剤師が日常業務にどう活かせるかをうかがいました
 減塩の必要性と課題
減塩の必要性と課題
——日常的に減塩することは,高血圧を予防し,その結果,脳卒中や心筋梗塞といった循環器疾患のリスク低下につながります。しかし,「減塩」を取り入れるのは容易ではありません。実際,「味が薄くておいしくない」「物足りない」「習慣として続けにくい」と感じる人が多いといわれています。こうした減塩に対する“ハードル”を,水田先生はどのように捉えていますか。
日本人は白米を主食としており,塩味のあるおかずと組み合わせて食べる習慣が根づいています。だからこそ,日本人は塩味をこよなく愛していて,減塩のハードルが高いのは当然といえます。
実際に「減塩」と表示された商品は日本では売れにくいのが現状です。これは他国と比較するとよくわかります。例えば,米飯を主食にしていない国では同じアジアの国であっても,健康意識が高く,減塩表示がある商品のほうがむしろ好まれるそうです。食文化の違いが,減塩に対する受け止め方にも大きく影響しているのです。
今年改訂された『高血圧管理・治療ガイドライン2025』でも,減塩は高血圧に対して強固なエビデンスに基づく基本戦略として位置づけられています。重要なのは,「いかに減塩を意識させないか」という工夫です。
 おいしい社会的減塩
おいしい社会的減塩
——水田先生が取り組まれている「おいしい社会的減塩」とは,どのような取り組みなのでしょうか。
減塩を効率的に進めるには,日本人がどこから食塩を摂取しているのかを知る必要があります。例えば,調味料からの摂取が多いと考えられがちですが,国際共同疫学研究INTERMAPによると,日本人の食塩摂取源の半分以上は,自分で調節できない加工食品に含まれる食塩です。したがって,個人の努力だけで減塩目標を達成するのは容易ではなく,産官学が連携した社会的な取り組みが欠かせません。
境港市を中心とした活動では,鳥取大学医学部,鳥取県産業技術センター食品開発研究所,地元の食品関係者が協力し,月1回のペースで定期的に話し合いを行っています。それぞれが専門性を持ち寄って役割分担しており,私は学会でのプロデュースや医学的な相談を担当しています。このように,多様な分野が連携しながら「おいしい社会的減塩」を推進しています。

水田 栄之助
山陰労災病院 循環器内科、日本高血圧学会評議員・実地医家部会中央委員
境港市の健康事業に携わり,「おいしい社会的減塩」プロジェクトを主導。アカモクうどんや減塩干物の開発,だし醤油の研究などを通じて,“こっそり減塩”社会の実現を目指している。さらにフレイル予防を目的とした「フレ飯」講演など,食を通じた健康寿命延伸の啓発活動にも力を注いでいる。
 こっそり減塩とは?
こっそり減塩とは?
——「おいしい社会的減塩」の中核的な手法のひとつとして“こっそり減塩”が位置づけられているとうかがいました。“こっそり減塩”とは,どのような施策なのでしょうか。その歴史や背景,世界的な取り組みおよび日本での現状について詳しく教えてください。
繰り返しとなりますが,減塩を長続きさせるためには,「いかに減塩を意識させないか」が重要です。また,先ほどお話ししたように「減塩」と表示された商品は日本では売れにくいという現実があります。だからこそ企業があえて商品に「減塩」と表記せずに販売する“こっそり減塩”が効果的なのです。
人間の塩味の感覚は意外に鈍感で,少しずつ減塩すれば味の変化に気づきにくいとされています。英国では国民に知らせずに主食のパンの塩分を減らしたところ,おおよそ10年で1日あたり食塩摂取量が約1.4g減少しました。その結果,脳卒中患者が40%,虚血性心疾患患者が42%減少するという大きな成果が報告されています1)。
この英国の成功例は,週単位で段階的に塩分を減らしても人間は味の変化に気づかないという研究結果に基づいています。人の塩味の感覚はそれほど鋭敏ではないといえるでしょう。
現在では世界各国が英国の取り組みを参考にしており,日本のコンビニエンスストアでも減塩の工夫が進められています。特にあるコンビニエンスストアは主力弁当などの減塩を進め,1年間で約100トンもの食塩使用量を削減したと公表しており,この取り組みは厚生労働省からも表彰されています。
 アカモクうどんの開発
アカモクうどんの開発
——山本製麺所(鳥取県境港市)が海藻の一種アカモクを使った「低塩あかもく生うどん」を開発し,産官学で検証・普及に取り組まれていると伺いました。開発のきっかけや,味や食感を保ちながら塩分を減らすために工夫された点について教えてください。
あるイベントにうどんを出すことになった際,アカモクの強い粘りに着目してうどんの生地に加えてみたところ,塩を使わずに面を成形できることが偶然わかりました。以前より鳥取大学医学部附属病院の栄養士さんに「塩をできるだけ使わないうどんを作ってほしい」と言われていたこともあり,アカモクうどんを作るようになりました。
一方で,世界各国で進められている“こっそり減塩”を山陰でも広めたいという思いから,「おいしい社会的減塩」プロジェクトが立ち上げられました。鳥取大学医学部や鳥取県産業技術センター食品開発研究所が協力し,産官学連携のかたちで取り組みを進めています。そのなかで山本製麺所が開発したアカモクうどんに対し,科学的な検証や評価が加えられ,社会的な成果として「低塩あかもく生うどん」が位置づけられることになりました。
うどんには通常,コシや保存性を保つために1食あたり約1gの食塩がつなぎとして含まれています。そのため,塩を入れなければうどんを作るのは難しいとされてきました。もっとも,近年では市販の「食塩ゼロうどん」や「減塩うどん」も登場しており,これらは製麺条件の工夫や小麦粉の配合調整に加え,加工でんぷんや増粘多糖類を利用することで麺の形や食感を保っています。
今回の取り組みでは,アカモクの強い粘性を利用することで,塩を加えずに麺を成形し,食塩含有量をほぼ0gに抑えることに成功しました。さらに,鳥取大学医学部解剖学教室が電子顕微鏡で麺の微細構造を観察したところ,でんぷん粒の変形が少なく,これがコシの強さに寄与していることがわかりました。また,表面のぬめりによるつるっとした質感が喉ごしの良さを裏づけるデータも得られています。
 麺屋やまもと——地元で愛される「低温あかもく生うどん」
麺屋やまもと——地元で愛される「低温あかもく生うどん」
山本製麺所が製造する「低塩あかもく生うどん」は直営店「麺屋やまもと」で味わうことができ,アカモクの粘りを活かして仕上げた麺は,地域の人々に広く楽しまれています。
アカモクうどんには「温」と「冷」の2種類があり,温かいうどんは太めの麺でしっかりとした食べ応えを,冷たいうどんは細麺でつるりとした喉ごしを味わえるよう工夫されています。
実際に口にすると,つるっとした喉ごしに加え,トッピングのアカモクの旨みが際立ち,地元で人気を集める理由がうかがえます。麺屋やまもとでアカモクうどんの他,通常のうどんやそば,ラーメンなども提供しており,製麺所直営ならではの幅広い味わいを楽しめる地元の人気店です。
麺屋やまもと――地元で愛される「低塩あかもく〈生〉うどん」
山本製麺所が製造する「低塩あかもく〈生〉うどん」は直営店「麺屋やまもと」で味わえる。アカモクの粘りを活かした麺は地域の人々に広く楽しまれている。温は太めでしっかり、冷は細麺でつるりとした喉ごしを楽しめるよう工夫されている。※価格は取材時点


- 創業70年の山本製麺所の直営店
- 営業時間:11:00〜14:00
- 定休日:日曜日
- 住所:鳥取県境港市朝日町66(〒684-0004)
- アクセス:米子市内から車で約35分/駐車場あり

 さらなる“こっそり減塩”への挑戦-だし醤油開発
さらなる“こっそり減塩”への挑戦-だし醤油開発
——アカモクうどんの開発に携わった経験を踏まえて,現在進めている取り組みについて教えてください。
現在の主な取り組みは,うどんにあうだし醤油(めんつゆ)の開発です。うどんが食塩ゼロであっても,めんつゆが塩辛ければ減塩の効果は十分に得られません。そのため,おいしく味わえる減塩のめんつゆを実現する必要があります。
減塩醤油の技術はすでに限界に近づいており,これ以上の減塩は難しい状況にあります。したがって,塩分を減らすためには醤油の使用量を少なくする必要がありますが,そうすると「味が薄い」と感じられてしまうという課題があります。そこで注目したのが「だし」です。塩分を抑えても塩味をしっかり感じられる「だし」と少なめの醤油でめんつゆを作ることができれば,おいしい減塩が可能になると考えました。
鳥取県産業技術センター食品開発研究所では,境港で水揚げされるさまざまな魚からだしを取り,味覚センサーを用いて塩分濃度を一定に揃えたうえで,どの魚種が最も塩味を強く感じさせるかを科学的に調べました。その結果,これまであまり利用されてこなかった地元の魚が,減塩に適した「だし」として有望であることがわかりました。
この魚は従来,臭みがあるなどの理由で利用しにくいとされていましたが,鳥取県産業技術センターが臭みを取る調理法を開発し,これを活用することで優れただしを得ることができました。このだしを活用しためんつゆが完成すれば,アカモクうどんはさらに一歩進んだ“こっそり減塩”を実現できると期待しています。
 “おいしい減塩”はどう受け止められているか
“おいしい減塩”はどう受け止められているか
——「低塩あかもく生うどん」をはじめとする“こっそり減塩”の取り組みは,地域の方々にどのように受け止められていますか。
「低塩あかもく生うどん」は,減塩を強調するのではなく,「おいしい」うどんとして提供されているため,地元では自然に受け入れられています。実際に「コシが強くて食べ応えがある」「喉ごしがよい」といった感想が多く寄せられており,減塩であることを意識せずに楽しんでいただいています。
このように“こっそり減塩”は,無理を感じさせずに生活に溶け込む点が大きな特徴です。単に「塩分を減らす」のではなく,「普段と同じように食べていたら,結果的に減塩になっていた」という環境づくりが,私たちの目標です。
 今後の展望
今後の展望
——厚生労働省「健康日本21」では食塩摂取量を1日7g未満に抑える目標が掲げられています。こうした国の方針も踏まえ,“こっそり減塩”が地域の食文化や産業,薬剤師の現場での実践にどのように結びつけていくことが望ましいとお考えですか。
減塩は高血圧管理に不可欠であり,健康寿命を延ばすための有効な手段です。しかし,高血圧は自覚症状に乏しいため軽視されがちで,症状が出たときには脳卒中や心筋梗塞といった重篤な状態に至ってしまうことも少なくありません。だからこそ,「健康日本21」が掲げる1日7g未満という目標は,社会全体で減塩を意識づけるうえで重要な指針になります。
今年改訂された『高血圧管理・治療ガイドライン2025』では,高齢者の血圧目標値について「年齢ではなく身体機能(ADL)で判断する」という画期的な改訂が行われています。寝たきりや介護施設に入所している人は,減塩よりもまずはフレイル・サルコペニア対策として「しっかり食べる」ということが大切です。
「一生の間に,塩をたくさん摂った人ほど病気になる」という考え方があり,若い人こそ減塩が求められています。家庭では「血圧が高い人」だけを減塩するのではなく,子どもを含めて「家族全員」で減塩に取り組むことが大切です。
こうした国の方針やガイドラインの変化を,地域の食文化や産業に取り入れることが重要です。“こっそり減塩”はその具体策のひとつであり,無理なく続けられる環境を整えることが,結果的に国の目標達成につながります。薬剤師さんには,患者に「我慢する減塩」ではなく「おいしく続けられる減塩」を伝え,実践に結びつける役割が期待されます。
 薬剤師へのメッセージ
薬剤師へのメッセージ
——これからの減塩支援を考えるうえで,薬局・薬剤師にはどのような姿勢が求められるとお考えでしょうか。
減塩というと「我慢」や「味気ない」といった印象を持つ方が少なくありません。だからこそ,「おいしく減塩する」「気づかないうちに減塩する」という視点が大切です。意識して努力するのではなく,自然に塩分を控えられるような工夫や仕組みを社会全体で整えていく必要があります。
薬局においても,「減塩してください」と強調するのではなく,こうした“こっそり減塩”の考え方を理解し,患者さんが無理なく受け入れられるような支援につなげることが望ましいと考えています。
また,患者の状態に応じた減塩指導も重要です。75歳未満の高血圧患者には積極的な減塩を勧める一方で,75歳以上で心不全を併発している患者には,まず食事摂取量を優先し,しっかり食べられるようであれば減塩を勧めるという二段構えの指導が効果的だと考えています。ぜひ,患者さんお一人おひとりの状況にあわせた支援を心がけていただければと思います。
引用文献
- He FJ, et al: Salt reduction in England from 2003 to 2011: its relationship to blood pressure, stroke and ischemic heart disease mortality. BMJ Open, 4: e004549, 2014